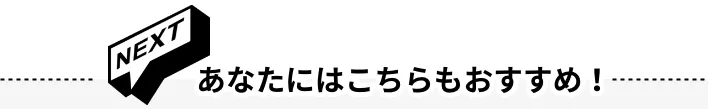小さな絵。しかも宗教画。美術館で大ぶりで華やかな絵に囲まれているとき、こんな少し地味な作品にはあまり興味が持てないかもしれません。しかし、よく練られた構図、それぞれの表す意味、どうしてそう描かれているのか、その繋がりが分かると見るのが楽しくなってくるでしょう。
ペトルス・クリストゥスはフランドル、日本ではフランダースとして知られる地域(大まかに現在のベルギーを中心としたフランスとオランダにまたがった地域)で活躍した画家。この地の三巨匠、ファン・アイク、カンピン、ファン・デル・ウェイデンの存在が大きく、そこまで有名ではありません。
主題はキリストが十字架から降ろされた直後の場面。右上に十字架の根元が描かれ、あたりに骨が散らばっていますね。キリストが磔刑に処されたゴルゴタの丘には「しゃれこうべの場所」という意味があり、伝説によるとアダムの墓があったとされ、絵画ではこのように頭蓋骨で表現します。手前にはキリストの受難のシンボルである三本の釘、ハンマー、やっとこが描かれています。
ぺトルス・クリストゥス「キリストの哀悼」
1450年頃 油彩・板 25・7 × 35・6cm(全体) メトロポリタン美術館所蔵
構図は、人物群を左右対称に横長の楕円状に配置。白い布の曲線がその流れを示し、画面を巡りながら一人ずつ確認できる構成です。中心に据えられているのは聖母マリアで、彼女を大きく見せるかのように聖ヨハネが後ろから抱えています。この聖ヨハネの真上を頂点に左下と右下の角を繋ぐ二等辺三角形を作ってみると、この中にマリアとキリストの頭部から布の端までがぴったりと収まり、二人の存在が強調されます。また、科学的な調査により、バランスが取れるよう、下描きの段階で各部位の微調整が行われたことが確認できています。
少し悪口のようですが、クリストゥスが描く人物は人形のようで手足が短く、目鼻立ちが小ぶりで、輪郭に動きがないと指摘されます。彩飾写本とファン・アイクの初期作品からの影響と考えられ、このような特徴は向かって左側でキリストを支えるアリマタヤのヨセフ、右側のニコデモ、聖ヨハネに顕著。対照的に細長いキリストの体躯や、駆け寄るマグダラのマリアの愛らしさを引き立てているともいえるでしょう。
本作が小ぶりなのは、個人の礼拝用に描かれたからと考えられます。この時代には、中世後期にはじまった「新しい信仰(デヴォティオ・モデルナ)」が広まり、キリストの受難を共感的に瞑想する祈りの習慣がありました。キリストの血の生々しい表現はその苦しみを感じさせるため。また、見る人が自分の生きる世界へと引き寄せて受け止められるよう、ヨセフとニコデモの服装は画家と同時代・同地域のもので、背景も明らかにキリストの時代のエルサレムではなくフランドルの風景が描かれています。聖母マリアの倒れ方が、キリストの姿と似ているのも偶然ではありません。類似したポーズに描くことで、マリアとキリストが同じ苦しみを味わったということを表現し、見る人の共感を増すためだったのです。
INFORMATION
「メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年」
大阪市立美術館にて2022年1月16日まで。巡回あり
https://met.exhn.jp/
●展覧会の開催予定等は変更になる場合があります。お出掛け前にHPなどでご確認ください。