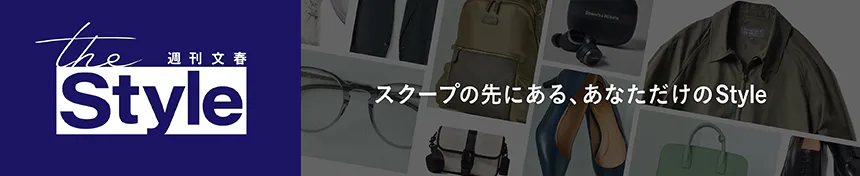「変化」が始まったのは70年代だ。倉敷市の瀬戸内海に面した水島臨海工業地帯には高度経済成長期以降、全国から若い労働者が集められた。地価が安くまとまった土地がある真備町には次々と住宅団地が造られた。水田は市街地となり、人口は2万人を超えた。
そうした状況に危機感を持つ住民もいた。明治期の洪水を体験した古老に「人が流されていくのを屋根の上で見ているしかなかった」と聞くなどしていたからだ。ある住民グループは「明治の水害以降、堤防は整備増強されてきた。ただ、万全ではない。伝承からすると最悪の場合には堤防の高さまで浸かる」と、様々な施設にこの高さでラインを引いた。
高いところでは6mにもなった。「そんなに浸水するものか」と笑う人もいたが、西日本豪雨ではまさにこのラインの近くまで浸った。
洪水のダメージは大きく、「もうこんなところに住めない」と転出する人もいて、真備町の人口は1割も減った。
被災地域の土地の安さにひかれて若いファミリー層が…
ところが、被災から年数が経つと2階まで浸かった地区に転入者が目立ち始めた。若いファミリー世帯が土地の安さにひかれて家を建てるようになったのだ。「浸水リスクを知っているのだろうか」と複雑な表情をする住民もいる。
被災者が建て直した住宅も平屋建てが多い。高齢で2階建てにするだけの借金ができなかったのだ。「子が独立したのに部屋が余る」「浸水より階段で転倒するリスクの方が高い」「次は早めに逃げるから大丈夫」などという声も聞かれた。
だが、前回並みの浸水なら、平屋は完全に水没して、逃げ遅れは死に直結する。これからさらに年が寄っていくというのに逃げられるだろうか。
これまでの災害では「ここで死ぬからいい」と避難を拒む高齢者が少なからずいた。よく考えなければならないのは、死ぬのは本人だけではないということだ。助けに来た人が「一緒に逃げよう」と説得しているうちに洪水は押し寄せてくる。