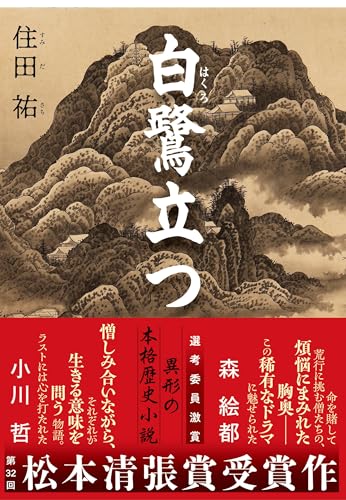年齢を重ねることで、違う強さが生まれてくる
――『白鷺立つ』の主人公の恃照は、48歳という年齢で2回目の千日回峰行に挑みます。鏑木さんご自身は年齢を重ねる中で、走り方や考え方に変化はありましたか。
鏑木:まさに、恃照の2回目の千日回峰行を、今自分がやっているような感覚です。30代の頃と同じことをしていても、深みが全然違います。
30代の頃は、自分の功名心や名声欲を満たすために、自分が勝てばいいという思いで戦っていました。それが変わったきっかけのひとつが、2011年の東日本大震災です。日本があんな状況になっているのに、自分は山を走っていていいのだろうか、と一時はずいぶん悩みました。でも、自分が走ることで少しでも誰かに勇気を与えられるなら、他人のために自分の身を尽くしたい、という思いが湧き上がってきました。
『白鷺立つ』でも、千日回峰行の前半の段階は自己と向き合う「自利行」、堂入り後は衆生の救済を行う利他の行としての「化他行」が描かれています。恃照は2度目の千日回峰行で、化他行について思い至ったと書かれていますが、そのあたりも自分の経験と重ね合わせて読んだ部分です。
アスリートにとっては、年を取って肉体が衰えていくのは、耐えられないことなんですが、還暦が近くなってきて、最近ではそれも悪くないなと思えるようになってきました。できなくなることが増えることで、自分を少しトーンダウンさせて、その隙間に色々なことを考える余裕が生まれる。若い頃の鉄板メニューが通用しなくなって、今の自分に合わせて試行錯誤しながらトレーニングをカスタマイズしていく。その過程が今は面白いですね。
昔のように速くは走れないけれど、自分が感じた辛さや情熱の持ち方を、言葉にして人に伝えられるようになった。そういう意味での「強さ」は、今の方があるのかもしれません。
――長く競技を続けていると、さまざまな出会いや別れがあるかと思います。
鏑木:……そうですね。実は、僕のトレイルランニングの仲間が、50歳でふたり、突然亡くなっているんです。そのふたりの死に直面した時、人間の人生は80歳、90歳まで生きられると勝手に思っていたけれど、明日死ぬかもしれないし、未来は保証されているわけじゃないんだと痛感しました。
彼らも、きっともっと色々なことにチャレンジしたかったはずです。だから、自分がやりたいと思うチャレンジは、いくつになってもやり続けたい。彼らが見たかった世界を、代わりに見てきてやるという思いが、57歳の僕の大きなモチベーションになっています。最近のレースでは、亡くなった仲間の一人のストックを使っているんですが、彼と一緒に走っているような気がして――それもすごく支えになっていますし、今の自分にできることを日々模索しながら、これからも精一杯走り続けたいと思っています。