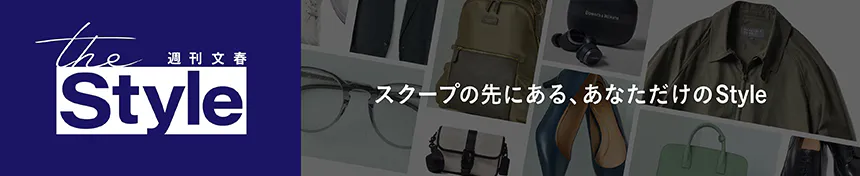教祖の裁判より中身のあった弟子たちの裁判
高裁で麻原が語る機会がなかったのは、残念と言えば残念だが、一審での態度や、彼が弟子の裁判の証人として呼ばれた際の対応を見る限り、控訴審が開かれても、「真相」を語る期待はまったく持てなかった。
教祖の裁判より、はるかに中身があったのは、弟子たちの裁判だった。多くの信者・元信者による様々な証言がなされ、事件に関する事実だけでなく、教団の実態、信者に対する心の支配の手法など、多くの事実が明らかになった。20回以上かけて被告人質問を行った者もいる。オウムというカルトに心を支配されていく過程をじっくり語った被告人もいた。裁判の過程で問題を何も感じなかったわけではないが、刑事事件としての事実は概ね解明されたと言えよう。
なされなかったカルト問題の解明
ただ、刑事裁判には限界もある。刑事責任を明らかにするという目的からはずれたことや、判断に必要とはいえない細かい事柄を延々と聞くわけにはいかない。しかし、社会と隔絶された教団生活の中での様々な事柄の積み重ねで、彼らは心を支配されていったことを考えると、カルト問題の解明という点では、事件とは直接関係の無い事柄もじっくり聞きたいところだ。それに、被告人が刑事裁判に集中している時には、充分に自らを省みる余裕もなかった者たちも、裁判が終われば、そうした時間も持てる。
ところが、いったん死刑が確定すると、彼らと外部とのつながりは遮断されてしまう。死刑囚が面会や手紙のやりとりをできる者は、家族などごく一部に制限される。本当は、裁判が終わった後に、心理学や精神医学、宗教学や危機管理や安全保障の専門家などが、刑事裁判とは異なるそれぞれのアプローチで、死刑囚となった教団幹部らに話を聞き、調査を行って、今後のカルト対策、テロ対策などに生かすべきだったと思う。それがなされなかったのは、本当に残念だった。
オウムを知らない世代が多数派となる時
歳月を経るにしたがって、記憶は風化していく。それどころか、一連の事件の時には生まれてもいなかった人たちが、今や立派な大人になって、社会に羽ばたいている。もう少しすれば、そういう人たちの方が多数派となる。
事件を知らない人たちにとっては、すでにオウム問題は「歴史」の範疇だろう。事情が分からない中で、「オウム事件は変な人たちが集まってとんでもない事件を起こしたんだろう」と思っている人たちも少なくないようだ。
オウムに集った、まじめで、善良な人たち
しかし、オウムに集ったのは、「変な人たち」ではなく、どこにでもいるような、ごく普通の若者だった。どちらかというと、まじめで、善良な人たちが多かった。
凶悪事件に係わった信者に、いわゆる「理系エリート」が少なくないのは、教祖がそういう人材を欲しがり、熱心に勧誘したからでもある。よく、「どうして、あんな頭のいい人たちがオウムなんかに行ったんですか」と問われるが、どんなに頭のいい人でも、悩む時はある。生まれてから死ぬまで順風満帆という人はいないだろう。
オウムには、自分の生きる意味はどこにあるのか悩み、生きがいや本当にやりたいことを探しあぐねて、オウムに引き寄せられてしまった人たちがいた。人間関係に悩み、居場所を求めているうちにオウムにたどり着いてしまった者もいた。そんな人たちに対して、麻原は「答え」を与えた。悩める人、迷える人にとって、何を聞いてもたちどころに「答え」を出してくれる彼は、非常に魅力的だったようだ。また、ヨガの修行がもたらす体験を、教祖の力による「神秘体験」だと信じ込まされた者も少なくない。
待っているのはアリ地獄のような心の支配
そうして、ひとたび足を踏み入れたら最後、なかなか抜け出すことができない、アリ地獄のような心の支配が待っている。元々は新興宗教には懐疑的だった人までもが取り込まれた。
頭の出来にかかわらず、不幸にしてタイミングさえ合ってしまえば、カルトには誰でも入りうるものだと思う。人間の心は案外もろいものだ。これが、オウム事件の1番の教訓ではないか、と思う。
程度の差はあれ、人の心を支配し、人生や人間関係を破壊してしまうカルトは、いつの世にも現れうる。日本最古の歴史書と言われる日本書紀にこんな話が載っている。
皇極天皇3年(644年)に東国富士川のほとりに大生部(おおふべの)多(おお)というシャーマンが現れ、橘の木につく芋虫を、「これは常世の神である。この神を祀ると、貧しい者は富を得、老いた人は若返る」と宣伝。人々に家の財宝を投げ出させ、酒や野菜や家畜を道ばたに並べ、「新しい富が入ってきたぞ」と連呼させた。話は都にまで伝わり、かぶれる人も出た。そこで、聖徳太子の側近とも言われる秦(はたの)河(かわ)勝(かつ)が成敗した。