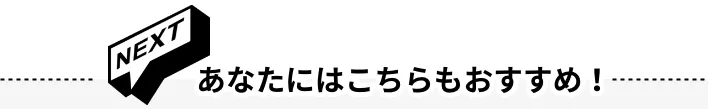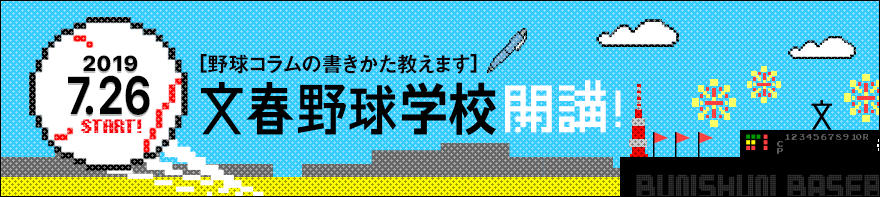まるで決して最終回の来ない大河ドラマ
その考え方を生み出す装置となっているのは春夏の甲子園大会とドラフト会議だ。同学年の選手たちは常に比較され、意識し合い、切磋琢磨する。各カテゴリーの大会で多くの名勝負が生まれ、ドラフト会議では残酷なまでに各々への評価が下され、さまざまなストーリーが付加されていく。だが、その序列は決して固定的なものではない。もちろん大谷翔平のように独走する選手もいるが、抜きつ抜かれつ、大外一気の下克上も頻繁に起こる。高校、大学、社会人、プロと厳しい生存競争と淘汰を繰り返しつつ、ユニホームを変え、メンバーがシャッフルされながらも20年以上に渡って競争は続く。選手たちが織り成すドラマを縦の時間軸で見届けること。これはある程度長いスパンで野球をみるものにとっては、こたえられない醍醐味の一つなのだ。
GC決戦に出場していたメンバーの中にもさまざまなドラマがある。12年前の夏。広陵でバッテリーを組んでいた野村と小林は甲子園の決勝で佐賀北の「がばい旋風」に飲み込まれた。満員の甲子園は広陵のアルプスを除いて佐賀北の応援一色。高校生には極めて酷な状況だった。8回に逆転満塁本塁打を被弾する直前、押し出し四球となった微妙な判定もあり、二人は悲劇の主役になった。だが、野村は昨年、その試合を振り返ったインタビューの中で「めちゃくちゃ悔しかったけど、日本一になれなかった悔しさがあったから大学で頑張れた」と語っている。甲子園大会を点で見れば、それはただの悲劇かもしれない。でも長い目で見れば、あの試合で負けたからこそ野村は最多勝をとるようなピッチャーになったし、小林はWBC日本代表の正捕手にまでのぼりつめたと考えることだってできるのだ。
14日の試合では二人は投手と打者として向き合い、小林が先制タイムリーを放った。高校時代から二人を見ているファンからしたら、また一つドラマが増えたとも言える。
小林はこの試合の勝利後、「戦いは続くと思うので、みんなでより一層、一つになって戦いたい」と話したという。小林が言っているのはもちろん今シーズンの残り30数試合のことだ。でも、たとえ今シーズンが終わったとしても戦いは続く。野球はとんでもなくロングランで、決して最終回の来ない大河ドラマである。その奥深さこそが野球というエンターテイメントの強みなのだと思う。
◆ ◆ ◆
※「文春野球コラム ペナントレース2019」実施中。コラムがおもしろいと思ったらオリジナルサイト http://bunshun.jp/articles/13154 でHITボタンを押してください。
この記事を応援したい方は上のボールをクリック。詳細はこちらから。