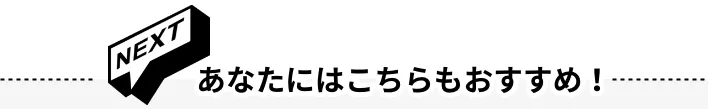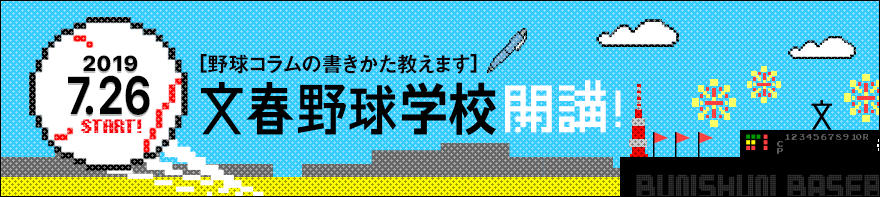お手本にしたのは西スポの記者だった
やりたいことを仕事にする。これ以上ない幸せであり、その気持ちは今も変わっていない。
ただ正直、最初の頃はきつかった。
だけど、恨み節を言う前に悪いのは自分の方だった。振り返れば反省しかない。
月刊ホークスには番記者という概念がない中、自分のワガママ(そもそも「編集者」は毎日現場に出るものではない)で球場に通いつめたが、いかんせん大学を出たての若造だ。ホンモノのプロ野球取材は大学新聞部とはワケが違う。そもそもロクに研修などもなく現場に出た自分は、社会人としての最低限の礼儀すらわきまえていなかった。
誰かが優しく教えてくれるような時代ではなかったし、もしあんな若者がいたら自分でも優しくできかねると思う(苦笑)。
しかし、我ながら負けん気だけは強かった。というよりも、つかみ取った夢を手放すのが怖かったという方が強かったのかもしれない。
やるしかなかった。覚悟を決めたとか腹をくくったというより、ただ毎日が必死なだけだった。
見て盗め。そういう時代だった。お手本にしたのは西スポの記者だった。一番気にして観察したのは、どのようにして選手や首脳陣、チームスタッフから信頼を得られるか。どんな質問をするかはもちろん、取材するタイミングやそれ以外の雑談の時間などをどのように作っているのか。あらゆるテクニックがそこにはあった。
まずは真似ることから始めた。一朝一夕で上手くいくはずはない。失敗はたくさんした。だけど、チャレンジなくして上達はない。やはり、やるしかなかった。
その過程の中で決め事を2つ作った。1つは無駄を積み重ねること。もう1つは、他人が当たり前に見るものは当たり前に見るし他人が見ないものも当たり前に見ることだった。
だから今も極端なほどの現場主義。また、私がファームにも足繁く通うようになったのは、昔は西スポの雁の巣情報がそれほど手厚くなかったからだった。
今まで以上に「ライバル関係」となるかもしれない
月刊ホークス編集部をわずか2年半で離れても、それ以降はフリーランスのスポーツライターとしてありがたいことに「タカ番」生活を続けられている。今年で22年目だ。
ある程度キャリアを積んでからも、私は西スポを勝手に“良きライバル”だと思ってきた。名物コラムの「好球筆打」を書く石田泰隆記者は、顔写真付きの署名記事で厳しい論調も恐れることなく書く。それでもチームや首脳陣、選手、スタッフから厚く信頼されている。誰にでも出来る仕事ではない。倉成孝史記者は少し前までキャップとしてタカ番をまとめ、工藤公康前監督の懐にぐっと入り込んでいた。この2人は同学年。刺激にならないはずがなかった。
朝起きて、西スポを読む。そんな当たり前の日常が明日4月1日からなくなってしまうのが今も信じられない。ただ、西スポは完全に消滅するわけではなくWebメディアとして新たにスタートをする。
タカ番スポーツライターの私にとっては今まで以上に「ライバル関係」となるかもしれない。でも、望むところだ。
それに我々タカ番が高め合うことは、すなわちホークスファンの幸福度向上に直結する。いよいよ開幕する2023年シーズン。より分厚く、もっと深くなるホークス情報を今まで以上に期待して待っていただきたい。
◆ ◆ ◆
※「文春野球コラム ペナントレース2023」実施中。コラムがおもしろいと思ったらオリジナルサイト http://bunshun.jp/articles/61709 でHITボタンを押してください。
この記事を応援したい方は上のボールをクリック。詳細はこちらから。