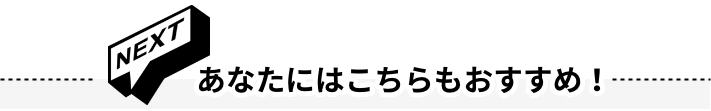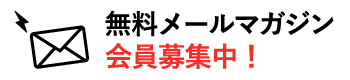子どもへの性加害は「平均週2~3回」小児性犯罪者のすさまじい実態
大森榎本クリニック・斉藤章佳(あきよし)さんインタビュー
――被害者に向き合うプログラムもあるのですね。
斉藤 小児性犯罪の被害者に実際に来ていただいて、被害体験を話してもらう「被害者からのメッセージ」というプログラムがあります。加害行為に遭う1次被害についてだけでなく、その後PTSDや不眠症状、うつ症状、自傷行為などの2次被害にずっと苦しめられることなどについても話してもらっています。こういった2次被害のことは、加害者は全く知らないんです。
こうしたステップを踏んではじめて、謝罪の準備ができると考えています。
――本当に長い道のりなのですね。
斉藤 長いですよ。彼らは、長年かけて作り上げてきたものの見方、感じ方を変えていく必要があるわけですから。
厳罰化だけでは、再犯防止の効果はない
――こうした小児性犯罪の治療は、日本では広がっているのでしょうか。
斉藤 小児性犯罪に特化した取り組みはありません。一部刑務所で性犯罪防止指導(R3)が行われていますが、対象者がかなり限定されているため、プログラムが必要であるにも関わらず受けることができない人がいます。
さらに、刑務所で実施されているのは認知行動療法の部分のみで、期間が短すぎる。出所後、治療を義務付ける制度もないので、効果的に行われている状況とはあまりいえません。
――小児性犯罪については、厳罰化や、前科者の情報公開を義務付けるアメリカのメーガン法導入などを求める向きもありますが、こうした施策に効果はあるのでしょうか。
斉藤 監視や監督、厳罰だけでは、再犯率は減らないと思います。メーガン法の三本柱は、GPS着用や、法定雇用主への情報公開、ネットでの顔や住所の公開ですが、そうすると前科者は定住も、定職につくこともできず孤立する。そのような状況では、自暴自棄になり再犯、というケースも出てきます。やるのであれば、きちんとした治療教育をセットにする必要があると思います。
「認知のゆがみ」はどこから来るのか
――最後に、読者に向けてメッセージはありますか。
斉藤 取材で小児性犯罪者の「認知のゆがみ」について話をすると驚かれるのですが、考えてみていただきたいのは、こうした認知のゆがみがどこから来ているのか、ということですね。
当クリニックには痴漢常習者の人のプログラムもありますが、彼らは「相手も痴漢されたいと思っていた」「やっている間に相手も気持ちよくなるんだ」「女性専用車両に乗ってない人は、痴漢されたい人だ」などと本気で思っているわけですよ。
でも、これって彼らの勝手な思いこみかというとそうではなくて、ここまで強烈でなくとも、似たような価値観は日本社会の中で流通しているんです。「いやよいやよも好きのうち」とか、「女性が性犯罪に遭うのは落ち度があったからじゃないか」とか。加害者はこういった価値観を、もとはといえば家庭や学校、社会やメディアから学んでいるんですよね。
社会の中にあるそういった価値観が変わらない限り、性加害する人たちはどんどん量産されていきます。目の前にいる加害者は、日本社会の縮図だといつも思っています。
写真=釜谷洋史/文藝春秋