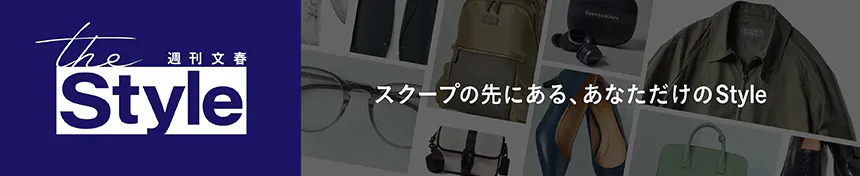サブカルチャー。この言葉を聞いて思い浮かべるものは、恐らく人によって様々だろう。ひとつの社会における主流文化に対して、その社会の一部の人々によって共有される副次的な文化……というような意味合いが、この言葉の一般的な使われ方ではある。
ただ、戦後日本社会においては、サブカルチャーという言葉はある独特のニュアンスのなかで用いられてきたと私は考える。一言で言ってしまえば、それは文化の脱歴史化・非政治化とでも言うべき、「脱臭化」のニュアンスである。
私=コメカと相方であるパンスとで構成される批評ユニット「TVOD」による初の著作『ポスト・サブカル 焼け跡派』は、時代を象徴する様々なミュージシャン・アーテイストに言及し、戦後日本のサブカルチャーを取り巻く文化的な精神史を描くことを試みた本だ。そしてその精神史の探求は、先述したような「脱臭化」の作法を活用し消費社会的状況を謳歌した日本が、いつの間にか「焼け跡」化していく軌跡を追うことになっていった。
以下に、本書のゼロ年代編で扱った椎名林檎の章を転載する。この作家は「70年代以降の日本のサブカルチャー」
◆
椎名林檎の本質が詰まった「ぎゅっとしててね」
コメカ ここまで、椎名林檎が「日本」のイメージを漠然とサンプリングし続けていることについて話してきたけど、また別の側面で、彼女が作ってきた作品というか言葉には、ある主題があると思うのね。
よく言われることではあると思うんだけど、「あなたはすぐに写真を撮りたがる あたしは何時も其れを厭がるの だって写真になっちゃえば あたしが古くなるじゃない」(「ギブス」)とか、「天上天下繋ぐ花火哉 万代と刹那の出会ひ 忘るまじ我らの夏を」(「長く短い祭」)、「噫また不意に接近している淡い死の匂いでこの瞬間がなお一層 鮮明に映えている刻み込んでいる」(「NIPPON」)、みたいな歌詞に顕れているように、瞬間的なもの・刹那的なものに本質的な美しさを見出す、みたいな志向があるんだよね。ある意味スタンダードなロック的価値観=「It’s better to burn out than it is to rust 錆びるより燃え尽きた方がいい」(ニール・ヤング「ヘイヘイ・マイマイ」)ではあるんだけど。
宇多田ヒカルの「どんなに良くたって信じきれないね」(「光」)っていう世界観にも近いところがあると思うんだけど、宇多田の「テレビ消して 私のことだけを 見ていてよ」(「光」)という苦みに対して、「i 罠 B wiθ U 此処に居てずっとずっとずっと 明日のことは判らない だからぎゅっとしていてね ぎゅっとしていてね ダーリン」(「ギブス」)みたいな「甘やかさ」が、椎名林檎の本質なんじゃないかなあと。