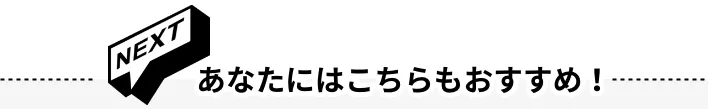肉親の愛憎の複雑さと芸術の残酷さ。それらを余すところなく描いて心を揺さぶる、娘と父の物語である。
父は、幕末から明治にかけて活躍した河鍋暁斎(かわなべきょうさい)。花鳥画から風刺画までを手がけ、描けぬものはないと言われた絵師である。不敬の絵を描いて投獄されたり、行き倒れの死人の顔を嬉々として写生したりと、反骨と奇行で知られ、「画鬼」を自称した。
娘は、その暁斎に五歳のときから絵を仕込まれたとよ。長じて暁翠(きゅうすい)という画号をもつ絵師となった。
物語は五十九歳で没した暁斎の葬儀から始まる。残された二百人を超す弟子をどうするか。暁斎が描くはずだった絵の依頼をどうさばくか。財産の整理は、家の始末は……そうした難題がとよの身にふりかかる。
とよには兄弟姉妹が四人いた。その中で自分と同じく絵の道に進んだのは、腹違いの兄・周三郎である。
暁斎が寝ついてから、とよは看病や見舞客の応対、代理の出稽古にと多忙を極め、絵筆を持つ暇はほとんどなかった。それに対し周三郎は、河鍋一門のことには頓着せず自分の絵に集中し、それは暁斎の没後も変わらなかった。
誰が暁斎の跡を継ぐのか、その最大のライバルである周三郎はとよに言う。お前には画才などない、暁斎は自分の片腕に使うために娘に絵を学ばせたのだ、と。
それを否定することが、とよにはできない。確かに父は絵のことしか考えない男だった。だが、絵だけが父と自分を結ぶ紐帯(ちゅうたい)なのだ。
――読んでいて切なくなる。とよにとって、描くことは父に負わされた重荷だった。だがその重荷がなければ、自分は何者でもない。父の才能を誰よりわかっている娘にとって、父に与えられた苦しみこそが、生涯の矜持なのだ。
兄のように男であれば、ただ絵に打ち込むこともできた。だがとよは、お金のこと、兄弟姉妹のこと、弟子のことなど、現実的な対処の責任をみずから負う。
父と娘の関係の、ひとつの普遍的な姿がここには描き出されている。父を尊敬する娘はしばしば、父のようになろうとするのではなく、父が望んだ役割を生きようとする。
とよは理解のある夫に恵まれ、子供を生んでからも絵を描き続ける。だが、表現することの苦しみをわかってもらえないことがつらく、離別してしまう。そして気づくのだ。自分のことを本当に理解できるのは、同じように、描かずにいられない宿痾(しゅくあ)を負った、あの兄だけではなかったかと。
物語の中心にいるのは、不在の父である。圧倒的な存在だった暁斎は、死後も絶対者として、残された者たちに君臨する。
とよはその父をどう乗り越えていくのか。あるいは折り合いをつけて生きるのか。繊細な筆で、作者はそれを描いていく。静かな声で語られる、血と芸術の壮絶な物語である。
さわだとうこ/1977年、京都府生まれ。2010年に『孤鷹の天』でデビューし、同作で中山義秀文学賞を最年少受賞。ほかの作品に、歴史時代作家クラブ賞作品賞と親鸞賞を受賞した『若冲』、舟橋聖一文学賞を受賞した『駆け入りの寺』などがある。
かけはしくみこ/1961年、熊本県生まれ。近著に『狂うひと「死の棘」の妻・島尾ミホ』『サガレン 樺太/サハリン 境界を旅する』。