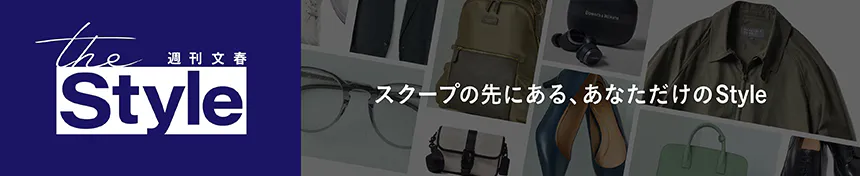西国巡礼のあと、文筆活動が本格的に
一九四五年、空襲で焼け出された河上徹太郎夫妻が白洲家に寄寓することになる。河上夫妻と白洲夫妻は軽井沢の別荘友達である。河上徹太郎は終日だまって虚空を眺めている。たまにピアノに向かうときも表情を変えずに無口で弾いているが、伊東に出かけるとなると急に潑剌とした顔になる。伊東には青山二郎がおり、そこに小林秀雄が来る。突如雄弁になる河上は青山二郎という人間の魅力を語り、小林秀雄の思考の様子、紡ぎ出される文章の魅力を語った。白洲正子はその友情に嫉妬を感じ、そこに分け入りたいと願った。彼女は能の世界では一つの達成を果たしていたが、文章を書くという行為においては未だ『お能』一冊を書き上げただけであった。
敗戦直後に白洲正子は文字通り、真正面から三人の中に分け入った。彼らに分け入る際に媒介となるのは骨董と酒である。三十六歳で酒を飲み始め、骨董を買いだした。場所は銀座、京橋、日本橋。欲望を捨象して骨董は存在しない。酒は人を修羅の世界に引きずり込む。敗戦直後の欲望と修羅の中に身を投じることによって、白洲正子は今までの殻を脱ぎ捨てようとしたのだと思う。何かを捨てないで、何が得られようか。腐心して手に入れた骨董も次から次に手放して、次なるものを求めた。拙(つたな)かろうが書いてみないことには人の批評は得られない。手ひどい批評を受ける連続であったようだが、己が批評の的になることによって、批評自体の真贋も判別する能力を身に付けたであろう。骨董が過去の世界のものだけなら、現代の工芸にそれをつなぐ仕事もしてみようという思いで銀座に「こうげい」という染織工芸の店も開いた。
一九六四年、五十四歳で西国巡礼の旅に出たのが一区切りなのであろう。以後、精力的に『栂尾(とがのお)高山寺 明恵上人』(一九六七年、講談社)、『かくれ里』(一九七一年、新潮社)、『近江山河抄』(一九七四年、駸々堂(しんしんどう)出版)、『十一面観音巡礼』(一九七五年、新潮社)、『日本のたくみ』(一九八一年、新潮社)、『西行』(一九八八年、新潮社)、『いまなぜ青山二郎なのか』(一九九一年、新潮社)、『白洲正子自伝』(一九九四年、新潮社)、『両性具有の美』(一九九七年、新潮社)等々の今も多くの人に読み継がれている本を陸続として発表した。『白洲正子全集』(二〇〇一~二〇〇二年、新潮社)全十四巻別巻一に収められている文章の大半は、中年期というよりも老年期に至って書かれたものである。