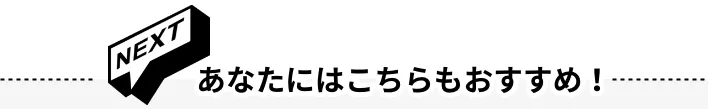ノーベル平和賞授賞式で日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)を代表して講演した田中熙巳代表委員は半生を被爆者運動に懸けてきた。「若い人たちに、核兵器廃絶は自身の問題だということを根付かせたい」。92歳になった今も、歩みを止めない。
13歳の時、爆心地から約3.2キロの長崎市中川の自宅で被爆。3日後、伯母らの安否を確かめるため爆心地に入り、多くの遺体を目撃した。「石ころや丸太ん棒のようになって死んでいた」と話す。
焼死体で見つかった伯母を含め、祖父ら親族計5人を失った。既に父は亡く、働きながら中学、高校を卒業し、東京理科大に進学。宮城県で東北大工学部の教員となり、1970年ごろ、運動に携わるようになった。
「死者の姿が脳裏に焼き付いている。核は兵器にも値しない悪魔の道具で、存在させてはならない」。85年に日本被団協の事務局長に就任し、体調不良で一時身を引いた時期もあったが、政府と交渉したり、国連で証言や原爆展の機会をつくったり、裏方として運動を支えた。2017年からは組織の顔である代表委員を務め、「被団協は私の生きる希望で、生きがい」と語る。
日本被団協は長くノーベル平和賞候補の一つと目されてきた。17年、核兵器禁止条約の実現に向け、共に行動してきた核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)が受賞した際、授賞式に招かれた田中さんは「ICANの仕事の土台は被爆者がつくった。被爆者も認められたと思った」と振り返る。
あれから7年。日本被団協への授賞を「核戦争の危機があり、核超大国の米国に気兼ねしている情勢ではなくなった。若いノーベル賞委員会委員長の大決断」と感じ、同時に「もう一度、被団協に活躍してほしいのだろう」と受け止めた。
日本被団協の結成から68年がたったが、唯一の戦争被爆国、日本は核禁条約を批准していない。「受賞を力に、核廃絶のため、いま少し動きたい」。共に活動し、先立った仲間たちの思いも胸に前を見据える。