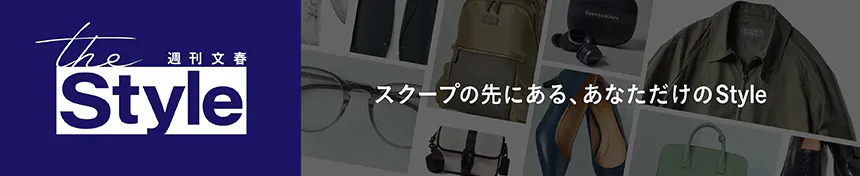2012年、19年に人気を集めた週刊文春「私の大往生」の新シリーズ。初回は今年デビュー60周年の加藤登紀子。理想の最期は「竜宮城にとどまって、タイやヒラメの瞬間の中に消えていく」ことだという。果たしてその心は? (幼少期編/次回はこちら)
今の私には、死ぬまでのプランは何もないんですよ。その時が来たら、「私の人生、ここで終わるのか」と思うだけ。どこまで続いてほしいとか、そういう欲望は一切ない。いつ終わってもいいんです。
ただ、自分のラストシーンを思い浮かべた時、病院や畳の上にいるのは嫌。私は旅が大好きで、仕事でも世界中を旅してきたから、じっとしていたくないのね。
憧れるのはロシアの文豪・トルストイの最期。彼は亡くなる前に家出して列車に乗り、途中下車した駅で倒れ、そのまま1週間後に駅長宿舎で亡くなった。すごくかっこいいよね。周りは困るだろうけど(笑)。私も、「いよいよとなったらどっか行っちゃうから、心配しないで」って、冗談交じりにみんなに言ってるの。
思えば、私の人生そのものが、答えのない旅のようなものでした。自分で選んだわけじゃないのに、時代のうねりの中、深い叫びの聞こえてくるところに運命的に出会ってしまう。
戦争が終わる1年8カ月前、旧満州のハルビンに生まれた時からその旅は問題を孕んでいた気がします。
終戦後、住む家を失った私たち一家は、無蓋貨物列車に揺られ、日本を目指しました。寝る時に広げる1枚の筵が私たちの「おうち」。命懸けの旅だったと聞いています。
まだ幼かったので、戦中、戦後のことはほとんど記憶にありませんが、中学生の頃には、「侵略者の娘として生まれた」という葛藤が芽生えていた。そんな思いを抱えながら迎えたのが、60年安保です。
〈この続きでは、学生運動全盛期の高校時代、「全日空857便ハイジャック事件」、「獄中結婚」し30年連れ添った藤本敏夫氏について語っている〉