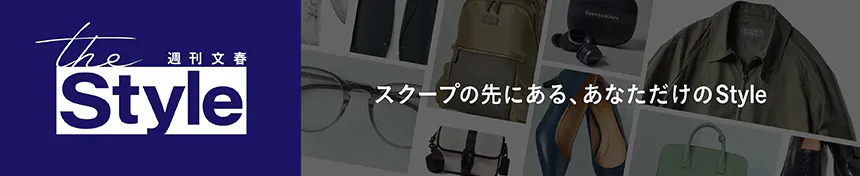文化3年(1806)、江戸。紅(くれない)の大傘も眩い琉球使節を絵に描く少年、徳太郎。定火消(じょうびけし)同心を務める貧乏御家人の家に生まれ、父が糊口をしのぐために描く扇絵を眺めるうち、自らも絵を描くようになった。ある時、葛飾北斎の狂歌絵本『絵本隅田川 両岸一覧』に衝撃を受ける。人々の声が聞こえ、いまにも動き出しそうだ。その絵が頭から離れない。徳太郎は北斎を訪ねる。
もう1人、かの使節を熱い眼差しで見る少年、染物屋の倅(せがれ)、孫三郎。「わっちの絵、見てほしい」と伝法な物言いで訪ねたのはやはり北斎の住まい。かくして北斎への思慕の念を懐くふたりは、出会った。のちに世に聞こえし画号でいえば――歌川広重、歌川国芳。
人々を熱狂させた稀代の絵師ふたりの邂逅と成長を描く『ふたりの歌川――広重と国芳、そしてお栄』を上梓した武内涼さんは、「もともとふたりの絵が好きで」と熱っぽく語る。
「広重の絵は『静』。たとえば『名所江戸百景 浅草金竜山』では、手前の大提灯の後ろに深々と雪が降る街。静謐な表現を得意としました。対して国芳の絵は『動』。本のカバー裏の『滝夜叉姫と骸骨の図』は、画面狭しと骸骨が迫る奇想絵。『讃岐院眷属(けんぞく)をして為朝をすくふ図』なんて、烏天狗や巨大な鰐鮫が躍動し、アクション漫画のようです」
絵だけではない。彼らの生き方にも魅せられた。
「広重は、最下層でも安定した武士の身分を捨て、自分の好きな絵の道に進んだ。身分制社会に抗う生き方はそう簡単なことではありません。一方の国芳は、幕府による厳しい文化統制の網を巧みにくぐり抜けた。遊女や役者を描くことを禁止されたら、雀や魚などに仮託して描くなど、江戸の人が見たいものを描き続けた。その反骨精神と商売上手なしたたかさたるや」
広重と国芳は同時期に活躍したが、調べるうちに、彼らが同い年だったことがわかり、興奮したという。 史実での接点はそう多くないが、「子供時代に出会いがあり、何かの理由で距離を置くようになったとしたら……そこから物語が一気に広がりました」。
徳太郎と孫三郎は、留守だった北斎には会えなかったが、ひとりの少女と出会う。葛飾北斎の娘、お栄。のちの応為(おうい)その人だ。
「互いを意識する少年、北斎譲りの絵の才を持つミステリアスな少女。彼らの関係を大胆に織り込みました」
物語の背景には、葛飾北斎。広重も国芳も、終生北斎を意識し続けた。
「広重が『東海道五十三次』で成功したのは、『冨嶽三十六景』で名所絵の可能性を拓いた北斎がいたから。北斎に強く影響を受け、リスペクトしつつも、広重は、和の情緒が表現された柔らかい絵を打ち出していきます。一方、国芳の北斎への愛情はストレートで。北斎のダイナミズムを取り入れるばかりか、実際に弟子入りしようとしたようです」
広重は、いまでは失われた江戸を描いたという。
「3人のドラマとともに、もう1人の主役として描いたのが江戸の街です。わずか200年前の、花鳥風月に溢れた庭園都市を身近に感じてもらえたら」
武内さんは作家になる前、映画監督を目指して、映像制作の現場に身を置いた。その頃の感覚が本作を書く上で役立ったという。
「なかなか芽が出ない焦燥感、不安定な仕事への不安。武士をやめて絵師の世界に飛び込んだ広重を共感を持って書けました。そして好きという思いで集まる仲間、そのかけがえのなさ。本来交わることのない武士と町人の人生の交錯を、楽しんでいただけたらと思います」
たけうちりょう/1978年、群馬県生まれ。早稲田大学第一文学部卒。映画、テレビ番組の制作に携わった後、2011年、『忍びの森』でデビュー。15年「妖草師」シリーズで徳間文庫大賞を受賞。22年『阿修羅草紙』で大藪春彦賞、24年『厳島』で野村胡堂文学賞を受賞。他著に『駒姫』『源氏の白旗』などがある。