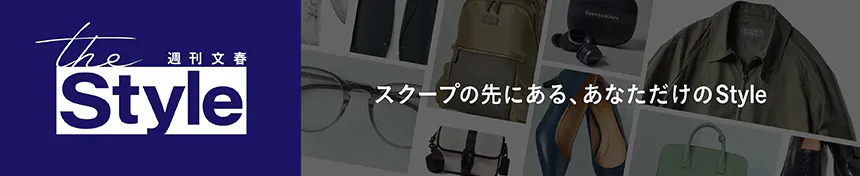読み始めるとすぐ、数年前に日本を震撼させた大事件が頭に浮かぶ。同時に当代きっての作家は現代の大事件をもモチーフにするのかという驚きも湧く。
202×年、N県の高校文化祭の式典。文部科学大臣が観衆の前で刺殺される。犯人の男(主人公)は大臣も関係するある宗教の家庭の二世。大臣は大物作家でもあるが、男は宗教と文学の両面に悩まされて生きてきた。逮捕後、男は手記を週刊誌に寄稿しはじめるが、そこには大臣への恨みが綴られていた。一方、その連載が終わりに近づく頃、その式典に列席していた作家が突如、事件のことを小説として発表する――。
読者はつい現実の人物などをあてはめながら読んでしまうだろうが、本作ではそんな仕掛けが随所にある。
主人公の父と大臣は作家だが、そこにはある文学賞も深く関係する。大臣は若くして新人文学賞を受賞するとスター作家となる。その先に政治家、大臣となっていく。この人物に憧れた主人公の父は評価もされるが、関係は暗転していく。
あるいは家庭や宗教。主人公の弟は体が悪く、母はその弟の快復を願って宗教に傾倒、2億円もの献金をし、家庭は崩壊していく。教団の名は世界博愛和光連合、通称愛光教会という。
本書では「宗教二世」の不遇という社会問題が物語を駆動させる。主人公の悲嘆は例の事件も想起され、理解もしやすいだろう。
だが、読み進めると、じつはそれらは舞台設定にすぎないことも見えてくる。本作の本当のテーマはさらにその先にあるからだ。
〈フィクションとノンフィクション、2つの物語がつながったときに見える景色とは。〉(本書の帯)
フィクションかノンフィクションか。そのあわいにこそ本書の醍醐味がある。
重大事件の犯人によって記される真実。家族を崩壊に至らしめる文学と宗教の関係。それらにハラハラしながら読んでいった先に、もう一つまったく別の角度から物語が語られだす。ただし、そこには「フィクション」とも記されている。
主人公の手記はノンフィクションのはずだが、作家の小説にもノンフィクションとして信じるに値する物語がある。読み返すと両者には複数の一致もある。
何がノンフィクションで何がフィクションなのか。俯瞰して見れば、本書の設定自体、ノンフィクションの素材のうえに書かれたフィクションでもある。
読者は主人公の不遇に悲しみや怒りを覚える中、いつしか戸惑いの世界に入っていく。何重にも構想された著者の世界の中で真実を探そうとしてしまうはずだ。
著者は一人称の語りが強みの作風だが、本書ではその才が幾重にも発揮されている。古くは芥川龍之介の『藪の中』、ポール・オースターの『幽霊たち』など古今東西の名作まで彷彿とする本作は、繰り返し読みたくなる物語性が構築されている。
みなとかなえ/1973年、広島県生まれ。2007年「聖職者」で小説推理新人賞を受賞。08年同作を収録した『告白』が「週刊文春ミステリーベスト10」第1位、09年本屋大賞を受賞。12年「望郷、海の星」で日本推理作家協会賞短編部門を、16年『ユートピア』で山本周五郎賞を受賞。近刊に『C線上のアリア』などがある。
もりけん/1968年、東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。著書に『「つなみ」の子どもたち』『小倉昌男 祈りと経営』などがある。