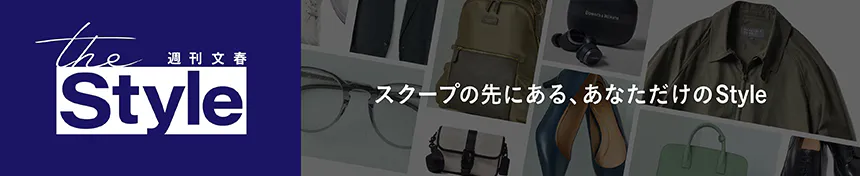『カフェーの帰り道』(東京創元社)で第174回直木賞を受賞された嶋津輝さん。デビューから直木賞を受賞されるまで、そして影響を受けた作家について語っていただきました。
◆◆◆
――第174回直木賞の受賞、おめでとうございます。受賞から一夜明けて、今のお気持ちはいかがですか。
嶋津 もう昨日は何が起きているかわからないというくらい、生まれて初めてのきらびやかな世界で。本当に眩しいなと思っているうちに一日が終わってしまいました。家に帰りましたら、興奮して3時ぐらいまで眠れず、今朝は10時過ぎに飛び起きるという……。慌てて身支度して今に至るという感じなので、今日はほとんど頭が回っておりません。ただ、めまぐるしく過ごしております。
2ヶ月に1回、短編を提出してください、と言われて
――嶋津さんは、2016年に「オール讀物新人賞」を受賞した「姉といもうと」を含む短編集『駐車場のねこ』(文春文庫)、初の長編で直木賞候補になった『襷(たすき)がけの二人』、そして今回直木賞を受賞された『カフェーの帰り道』という3作を刊行されています。『駐車場のねこ』は直木賞の受賞前から大変評判がよく、ロングセラーになっていますね。
嶋津 数日前にも増刷のご連絡をいただいて躍り上がったばかりです。この短編集には7作が収録されているのですが、オール讀物新人賞をいただいた後、最初の担当編集者に「2ヶ月に1回、短編を提出してください」と課題をいただきまして。順調に書ける時もあれば、2ヶ月のうち1ヶ月と20日ぐらいはうんうん考えるばかりで、残りの10日でなんとか書く、みたいな時もありました。幸いにして「オール讀物」に割といいペースで掲載していただき、2019年に書籍にしていただきました。単行本の刊行時は『スナック墓場』というタイトルだったものが、文庫化で『駐車場のねこ』というタイトルになり、猫ブームにも乗って、ありがたいことに長くよんでいただけているという状況です。
――2作目の『襷がけの二人』では初めて長編に挑戦されました。
嶋津 それまでは現代ものしか書いたことがなかったんですけれども、これも編集者に「近現代ものに挑戦してはどうか」というお話をいただいて。その時に、中島京子さんの『小さいおうち』をご紹介いただいて読んだんですね。「ああ、こういう書き方があるんだ」と、とても感銘を受けました。そこを目指すというか、そこまでは到達できないと思いつつも、私も日常を緻密に書いていく長編を書いてみたいなと思い、挑戦しました。
ただ、前半はとにかく筆が進まなかったです。女中さんと若奥様が生活をしながら絆を深めていくパートは、どうしてもある程度平和な世界を描きつつ、その絆が強まるところを表現したかったので、あまり大きな事件は起こさず、でも、読むに堪えるものにする、という塩梅が非常に難しくて。日常を書くのって難しいなとつくづく思います。
――そして、いよいよ今回の受賞作『カフェーの帰り道』です。どのように執筆を進めていかれたのでしょうか。
嶋津 はじめは長編を書けたら、と思っていたんですけれども、自分はプロットがうまく書けないというのもあって、連作短編の形で進めてみようということになりました。ただ初めからラストを意識した書き方にはなったと思います。「女給」というものを調べていくと、ほぼ明治から戦後ぐらいまでしか存在しなかった職業ということが分かったので、その時代を書こうと思いました。
感情の起伏がとても激しくなった。「青春だな」って感じることが多いです
――嶋津さんは40歳を過ぎてから小説を書き始め、56歳で直木賞受賞となりました。人生の後半で生活が一変したことについてはどう思われていますか。
嶋津 それまでは、いわゆる事務系の会社員を転々としてきました。40代にもなると、そんなに人から怒られることもなくなるし、社内の嫌な人というのがだんだん少なくなってきます。そのタイミングで小説の世界という新しい世界に入ると、本当に自分は新人なわけで、これといったアピールポイントがあるわけでもなく、五里霧中というか、風前の灯だったと思うんです。それなりに苦労もしましたし、叱られることもあったり、時には軽んじた扱いを受けることもあったり。そういうことも含めて、なんだか「青春だな」って感じることがすごく多かったです。
もちろんネガティブなことだけじゃなくて、雑誌に作品が載ると飛び上がるほど嬉しかったりとか、感情の起伏がとても激しくなったんですよね。この年でこういうところに到達できたっていうのは、本当に面白い経験かなと思います。