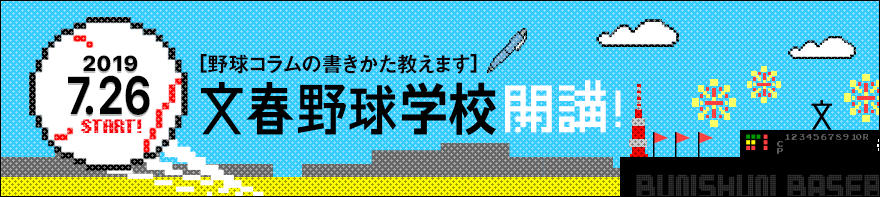東京ドームのマウンドには晩年の木塚敦志がいた。10年ほど昔のことである。当時はまだ熟れたお兄さんぐらいだった若造の俺は、人生で初めてバックネット裏の特等席なんてところにいた。旧知の読売新聞関係者に泣いて頼み込んだペアチケット。当時いい関係になり掛けていたきれいだけど野球を知らないお姉さんと、それ以上に素晴らしい関係になることを志してのナイトゲーム。
「あの人、なんであんなに暴れてるの? 落ち着きがなくて、めちゃめちゃうけるんですけど」
ギョッとした。マウンド上にはいつものルーティンを続ける木塚の姿があった。スパイクでマウンドに穴を掘っている。まだ掘る。どこまでも低い体勢から躍り上がるように投げる。猛る。キャッチャーの返球を奪い取る。大きくジャンプ。股割。滾る気合いにうっとりとしていた。ああ、これだ。これぞ、木塚の世界だ。
それを見ながら彼女がクスリと笑う。違うんだ。木塚にとって勝負は”やるかやられるか”命のやり取りと同じなんだ。誰にどう思われようが関係ない。こちらの気魄に、バッターが少しでも嫌がってくれたなら。打ち取れる可能性が1%でも上がるなら、たとえ笑われたとしても、ボールがいかなくたって、その時に何ができるのか“一番いい方法”を死に物狂いで探して、もがき続ける。木塚はそういう男なんだ。
バカ正直なまでに勝負に誠実に実直に接してきた男なのだ
俺は木塚に弱い。今でも木塚を遠目で見ただけでも、うっすら涙がにじんでしまう。高校時代の甲子園。9回裏の誰も捕れない不運なポテンヒットで負けたことを「何で負けた?」と死ぬほど考え抜き、大学時代は魂を入れるため本名の敦士に「心」を入れて敦志にした。その勝負に自分は本当にベストを尽くしたのか。後悔するなら、負ける前になぜ気づかないのかと、バカ正直なまでに勝負に誠実に実直に接してきた男なのだ。
優勝なんて口にも出せなかった2000年代後半。シーズン早々に最下位に落ちては上昇の気配すら見せず、不名誉な記録ばかりが追いかけてくる日々。木塚は毎日毎日毎日同じような苦しい展開の中に出てきては、気合いのルーティンを繰り返していた。それは同じように負けを重ねるチームに、苦境を打破できない自分に、怒りをぶつけるように。悪い循環に飲み込まれるように自滅を繰り返す若い投手たちに「俺がやってやるよ、見とけ!」と挑発するように。
中継ぎだけで490登板。毎年酷使と故障を交互に繰り返す度に、ボールは目に見えて衰えていった。段階が進むたび、穴の深さが、サインを見る時の姿勢の低さが、負けねえという気合いが色濃くなっていく気がした。
東京ドーム。プレイが掛かると、木塚のボールは右中間へ簡単に弾き返された。再び交代のコールを背に受けると、木塚は肩を落とすでもなく、ダッシュでベンチへと戻っていく。「穴掘りに来ただけじゃない」。彼女が言った。おそらく、軽い気持ちだったのだ。それはわかる。だが、いっちゃいけん。それいったらおしまいじゃ。
「黙っとけ。お前に何が分かる」
……叫びたかった。でもそんな度胸も気合いもないので、口だけパクパクしながら席を立った俺は、逃げた。総武線に腰を下ろし、ガクガク震えながら「急な仕事が入ってしまったので帰ります」とメールを入れる。そして、めそめそ泣いた。木塚は人生を賭けて勝負してんだよ。なのに結果で黙らせられなかったことが、彼女の言葉を否定できなかったことが、悲しくて、悔しくて気絶しそうだった。
それから間もなくして、木塚は現役を引退した。
球団はすぐに投手コーチのポストを用意した。就任早々「若い選手につきあうなら寝る時間なんか考えていない」と言ってるのをどこかで聞いた。自分の経験を、後悔を、ブルペンに残して来た火を絶やさぬよう、コーチとしてあらゆる角度からめちゃめちゃ勉強して、思いがある選手には、燃え尽きるまで投げられるよう手を尽くした。
キャンプのブルペンでピッチャーのボールを受けながら鼓舞する声を聞くたびに。シーズンのドキュメント映像で、ブルペンで祈るように気合の声をあげてリリーフを送り出す姿や、酒に酔ったリリーフエースが子供みたいに泣きながら愚痴をこぼすシーンもそうだ。どうにかしてやろうと願う木塚の言葉。そして、若い投手から木塚を信頼する声が出るたびに、外から眺めることしかできない俺のようなただれたファンにも確信に近い信念ができあがるのだ。このチームがどんな方向へ舵を切ろうと、若い投手がどんなトラブルや不調に出会ってしまったとしても、木塚がいれば大丈夫。木塚がいれば最善の解を出すために死ぬほど考え抜いてくれる。投手の辛苦を共に悩み、悲しみだって背負ってくれる、と。