少年の将棋への思いは、海峡を越えはるか東を向いていた。翔ぶか、留まるか。深浦康市は12歳で決断した。

第七章 終わりなき春 其の一
2007年の9月24日、深浦康市は東京から下りの電車に揺られていた。第48期王位戦。3勝3敗で迎えた第7局、その舞台となる神奈川県秦野市までは都内から2時間ほどだったが、道中ではある思いが何度も脳裏をよぎっていた。
これが最後のチャンスかもしれない……。
深浦は35歳になっていた。20代前半から半ばにかけてピークを迎えるといわれる棋士の世界で、30半ばで初タイトルを狙おうという自分に、これから何度もチャンスが訪れるとは思えなかった。それだけこのタイトル戦に辿り着くまでの道程は長く過酷であった。
1990年代から2000年代の将棋界において、タイトルを狙うということはほとんど羽生善治と戦うことを意味していた。だが、どの棋戦においても羽生がいる場所へたどり着くまでには幾多のハードルがあった。あと一歩というところまで迫っても、森内俊之や佐藤康光といった羽生世代の強豪が門前の仁王像のように立ちはだかっている。深浦は何度も道半ばで跳ね返されてきた。勝率が7割を超えた年でもタイトル戦の挑戦権は手にできなかった。だからこそ、やっとの思いでつかんだこのチャンスを逃してはならないという思いがあった。
翌9月25日の朝、第48期王位戦第7局は始まった。決着局の舞台となる鶴巻温泉の老舗旅館「陣屋」は秦野市の住宅街にひっそりとあった。1万坪の庭園が庵を囲み、非日常の静けさを生み出している。半世紀以上前には「陣屋事件」の舞台となった。名棋士、升田幸三をめぐる対局ボイコット騒動である。そこにいるだけで将棋史を感じることができる対局場は深浦の気持ちを高ぶらせた。
初回登録は初月300円で
この続きが読めます。
有料会員になると、
全ての記事が読み放題
-
月額プラン
1カ月更新
2,200円/月
初回登録は初月300円
-
年額プラン
22,000円一括払い・1年更新
1,833円/月
-
3年プラン
59,400円一括払い、3年更新
1,650円/月
既に有料会員の方はログインして続きを読む
※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。
source : 週刊文春 2023年9月21日号








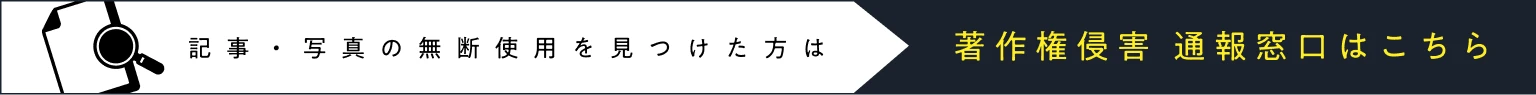
 トップページ
トップページ お気に入り記事
お気に入り記事 文春記者トーク
文春記者トーク マイページ
マイページ