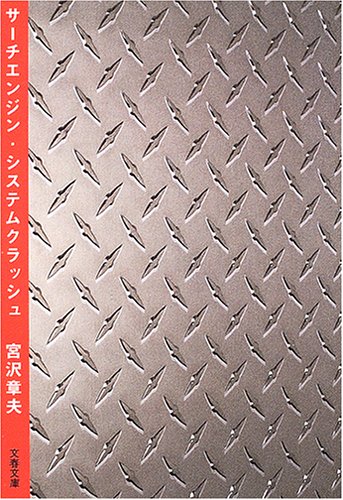忙しくても1分で名著に出会える『1分書評』をお届けします。
今日は尾崎世界観さん。
◆ ◆ ◆
最近、ツイッターに尾崎の書評は書評じゃないと書かれているのを目にする機会が増えた。そうか。じゃあ書評というのはなんだろう。ただ本の中身に触れたら書評になるのだろうか。やってみよう。
主人公は酷く焦っている。何かに追い立てられるように、何かにすがりつくように、当てもなく街を彷徨い続ける。それは何かを見つけたいと思いながら、何も見つからないことを願っているような。読者は猥雑な池袋の街を彷徨う主人公に自分自身を投影して、いつしか安らぎすら覚えるだろう。まるで自分の身代わりに、物語の中で主人公が焦燥感を連れて迷い歩く。そしていつしか読者は不安になるはずだ。主人公が何かを見つけてしまうことを。そうなって自分だけが物語から取り残されてしまうことを恐れるだろう。
主人公と同じく、読者も願うはずだ。何も見つけることなく、このまま彷徨っていられますようにと。出来る事なら、このまま変な人になってしまえるようにと。登校時間の迫った朝に、怠い身体が体温計の液晶に高い数値を叩き出すのを信じて、祈るように体温計を見つめるように。体温計の数値を振り切った場合は学校を休めて、気を振り切ったら人間を休める。まともな人間でいることは疲れるから。人間自体を休んでしまえば楽だ。
曖昧に捻れていく記憶の中に、心地の良いぬくもりを見つけて、いつまでもその場から離れられなくなる。いつしか、焦燥感を連れていた主人公は読者を連れて彷徨うことになる。そして読者はそれに気づかれないように、そうっと静かに物語を読む。やがて、何の前触れもなく物語は終わる。池袋の雑踏に主人公を見失って、心細くなって、意味もなく奥付の細かい部分に目を通したりする。いつまでも解けないクイズの答えを考えるフリをして、捲れないページを捲る。
ほら、やっぱりこうなった。なんか嫌だ。こんな偉そうに、知った風に本を語るんじゃなくて、本に動かされた自分の気持ちを書きたい。
金がない苦しいあの時期に、この本を散々迷ってレジに持って行ったことでどれだけ大きく気持ちが動いたかを。影のようにくっついてきて、何をしても離れられなかった自分自身を捨てて、その向こう側を少しだけ見れた。そんな気持ちにさせてくれたことを。