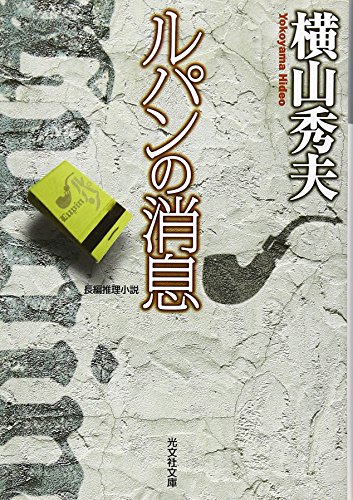組織を離れて、組織の本当の姿が見えてきた
――そして書き上げた『ルパンの消息』がサントリーミステリー大賞の最終選考に残った時点で、新聞社を辞めたわけですよね。
横山 賞を獲ってから辞めればよかったわけで、最終選考に残ったところで辞めたのはただのええ格好しい。というか、ルパンを書いた時点で決めていたんでしょうよ。「号泣する準備はできていた」じゃなくて、「辞める準備はできていた」ということだと思います(笑)。
上毛新聞の東京支社の人が、この賞の主催者に知り合いがいて、「上毛新聞の横山さんが最終選考に残っている」と聞いたらしいんです。会社には横山という人間がもう一人いたので、そっちが問い詰められたらしい。まさかこっちの横山が書いたとは誰も思わなかったようです。帰属意識の強い人間だと思われていたし、実際そうでしたから。会社からすると横山秀夫がフィクションを書いたのは、ありえない裏切り行為に映ったかもしれません。「新聞記者はかくあるべし」を次世代に向かって言い続けていく男だと信じていたろうし、新聞という1行たりとも嘘を書いてはいけない世界で生きてきた人間が、なんの前ぶれもなく最初の1行から最後の1行まで虚構の話を書いたわけですから。
――1991年に『ルパンの消息』が第9回サントリーミステリー大賞の佳作に。でも本は刊行されず作家デビューとはならなかった。これが刊行されるのはずっと先です(2005年刊行/のち光文社文庫)。91年から98年に「陰の季節」で第5回松本清張賞を受賞するまでは、漫画原作の執筆などを手掛けていたそうですが、その間、小説は書いていらっしゃったのですか。
横山 書いては応募して落ちていました。三次選考、最終選考と、いいところまではいくんですが、最後の壁が高かったですね。漫画の原作は会社を辞めてからデビューするまでの7年間に断続的にやっていました。よく「修行期には漫画の原作を書いていた」みたいに言われるんですが、自分としては小説とまったく変わらず全力投球していました。当時の『週刊少年マガジン』は週に450万部という化け物雑誌だったんです。競争が激しかったですね。何回かアンケートでビリになると、何カ月も先までシナリオが出来ていてもたちまち連載が打ち切りになるんですから、常に真剣勝負でした。言うまでもなく、日本の漫画はレベルが高く、人間心理から構造から、研究しつくされていますから学ぶことも多かった。結局1本のヒットも飛ばせず、心残りになっていますが。
――どういう話を作ったのですか。
横山 山岳漫画やテレビキャスターの話などいろいろやりましたが、どれも8週くらいで打ち切りになっちゃいましたね。一番長く携わったのはドキュメント漫画でした。当時『少年マガジン』では毎年夏に戦争の語をドキュメント漫画にして掲載していて、その取材とシナリオを担当していました。取材費が潤沢だったので、日本全国、軍の関係者を探して飛び回っていました。ハワイにも日系二世部隊の人たちの話を聞きに行きました。一度もビーチに寄らずに4泊6日。真面目が取り柄でしたね(笑)。
――その後1998年に松本清張賞を受賞する「陰の季節」では、警察の刑事部ではなく警務部を舞台にしたことで新しい警察小説だと評価されました。警察という組織の中で働く人々の姿を描き出したのは“発明”だと思うのですが、どういうきっかけだったのですか。
横山 組織にいる時は、組織のことなんかわかりきっていると思っていたけど、組織を離れてみて、改めて外から見つめる長い時間を得て、そうしたら組織の本当の姿が見えてきた、というようなことではないですかね。組織と個人の関係性に改めて興味が湧き、それを主題に小説を書こうとするなら、刑事を主人公に据える必然性はないわけで、むしろ管理部門を選ぶほうが自然だったので生まれた作品とも言えると思います。
私の経験を話せば、新聞社を辞めた時、組織の呪縛から解放されたと感じましたが、それは幻想でしたね。アルバイトでもなんでも、仕事をして金を得る当たり前の生活をしていれば誰でも悲哀を託ちます。どんな業界にもしきたりなりしがらみなりが存在し、もっと言えば日本という国そのものが1つの組織体なわけですから、そこからはなんぴとといえども逃れられません。じゃあ、それを認めた上でどう生きようか、みたいなことを考えるようになりましたね。
そうすると逆に、警察や会社のような純然たる組織も捨てたもんじゃないなあ、とか思ったりするわけです。たとえば、組織は人を輝かせる舞台装置として素晴らしくよくできていますよね。どんな職種の人でも、自分の職種にまったく興味のない人、わからない人に「いい仕事してますね」などとトンチンカンに褒められても嬉しくありませんよね。同じ組織の中で、同じ方向を見つめ、同じ苦労をしている人に「いい仕事をしたね」と言われたら言葉が心に入ってくる。承認願望は、的を射たものでなければ満たされませんからね。組織は人を蝕むことも多いけれど、人を輝かせる材料にも事欠かないという話です。