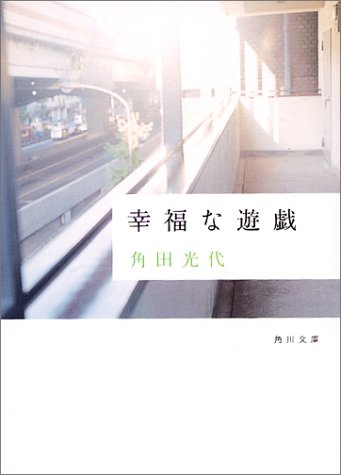小説量産のなか「書きたいものじゃない」
――そして『すばる』に応募して………。でも在学中に少女小説の賞を受賞してジュニア小説家としてデビューされていますよね。
角田 はい。『すばる』で最終に残ったんですが、あの賞は最終に残ると担当編集者がつくんです。その時についてくれた片柳治さんという編集者が「あなたは19歳で若いから、少女小説の賞に紹介してあげる」って。「新しい小説をもうひとつ、若い読者向けという気持ちで書いたら、3次選考までをすっとばして最終選考にいれてあげる。最後は選考委員が決めるから、必ず賞が獲れると言えないけれど、そこまではやってあげる」と言われたんです。もうとにかく仕事がしたかったので「じゃ、書きます」と言ってすぐ書いて、20歳になった夏に賞をもらったんです。
――その2年後に『幸福な遊戯』(91年刊/のち角川文庫)で海燕新人文学賞を受賞して再デビューされるわけですが、その経緯というのは。
角田 当時、本当に過酷な世界だったんです。これこそ、まるで小説のようだと思いました。もうちょっと若い子向けの小説界があるだけだと思っていたら、全然違う。4か月に1回、250枚以上の長編を書かなきゃいけないんです。その合間に隔月刊の雑誌が出るから、30~60枚の短篇を書く。それを休ませてもらえないんですよ。「ちょっと卒論が」と言っても、休ませてもらえない。で、売上が重視されるんですけれど、私のはとにかく売れなかったんです。売れないから次はああしてほしい、こうしてほしいと言われる。「恋愛をいれてほしい」「登場人物を全員高校生にしてほしい」とか注文がどんどん来て、「こういうものが書きたかったわけじゃない」という気持ちが常にありました。
その時に、誰かに「もともと『すばる』に書きたかったんでしょう? ここでいいものを書いていれば、いつか『すばる』で書ける作家になるよ」と言われたんですけれど、「ないな」って思ったんです。ここでいくら頑張っても、私に限っては、それはないな、って。
当時、少女小説はすごく売れていたので、ほぼ新人でも1年で1000万円稼ぐと言われていたんです。でも、1000万稼げるくらいの部数が出たとしても、絶対に『すばる』で書けるようにはならないということを、2年かけて分かったので、これは抜け出さないといけないと思い、最初は『フェミナ』という雑誌に応募して……。
――ああ、江國香織さんや井上荒野さんが第1回を受賞された賞ですね。
角田 私はその第3回に応募したんです。名前をかえて。そうしたら、その最終選考に残ったんですね。最終では落ちたんですけれど、その時に「少女小説は辞めよう」と意志を固めたら、編集者に呼び出されて「君はもううちで書かなくていい」と言われて。まあ、私が言うより先に、向こうに事実上解雇を言われてしまいました。
――それで、『海燕』に応募して、受賞して。たいへんな学生時代でしたね。
角田 本当ですよねえ。働いて、働いて(笑)。
――その後、どういうものを書いていくのか、ご自身のなかでもいろんな変化があったと思いますが。一般文芸だけでなく児童文学も書かれていましたよね。
角田 23歳でデビューして、29歳まではよかったんですよね。で、29歳くらいから辛くなってきました。ずっと文芸誌から依頼が引きも切らずにあったのがだんだん減ってきて、賞の候補にもならなくなってきて、まずいと思って、これはちょっと声をかけられるものをなんでもやって幅を広げていかないと、というのがありました。その時ちょうど児童文学の依頼があったり、絵本の雑誌「MOE」から依頼があったりして、読み手の層を考えていろいろ書くようになったのが30歳の時ですね。
30歳で幅を広げようとしたのは、やはりもう純文の雑誌にほぼ見放されつつあるなという気持ちがあって、自分が書いているものが悲鳴をあげているように思えたというか。もう全然書けないなというのがあったんです。30歳から33歳までの間は何を書いても全然よくならなかった。その時に編集者の人が来て、私の知らない雑誌に書いてほしいと言われたんです。「今までのような書き方じゃなくて、ページをぐんぐんめくらせるような小説を書いてほしい」って。それが『別冊文藝春秋』に当時いた、大嶋由美子さんだったんです。その時に目から鱗が落ちる思いでした。「ページをめくらせる小説か!」って。それは考えたことがなかったんです。いかに一文をじっくり書くかみたいなことにとらわれ過ぎていたので、まったく別のものを見せられた気がして、それで『空中庭園』を書いたんですよね。で、書いたら楽しかったんです。評価も思いがけず良かったので、そこからは私の知らなかった小説誌というものがわーっと依頼をしてくれて、そこで世界がまたぱーっと開きました。