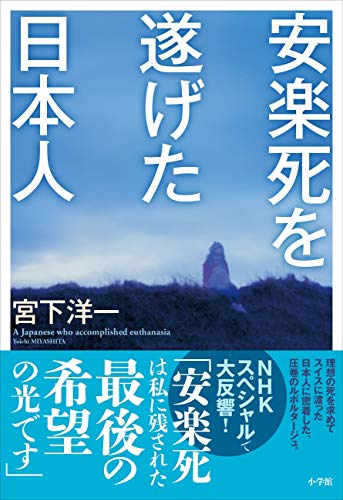1年後のことだった。この女性の安否が気になり、彼女の安楽死を担当していたスイス人医師に話を聞くと、「条件不足だったので、一旦、国に帰ってもらうことにした」と言った。そして、こう付け加えた。「好きな人ができたみたいで、死ななくて良かったという手紙がしばらくしてから送られてきたのよ」。
ここにとても重要なことが隠されている。
いわゆる「難病患者」たちの人生は、周囲の人間が勝手に、憐れんだり、悲観したりする類のものではないということだ。たしかに生活する上での苦難は人より多いかもしれないが、それこそ医師や周囲の手助けを借りながら、健常者以上に幸せな生活を享受している例をいくらでも知っている。
本当にこの京都の女性には死することしか、正解はなかったのだろうか。2人の医師は、別の選択肢について女性とともに考えたのだろうか。致死薬を投与したことが、1人の人間の死をもたらしただけでなく、この病に対する負の意識を社会に植え付けてしまった罪に気付いているだろうか……。
私が何を問おうとも、患者本人はもはやこの世にいない。本人の願いが叶ったのだから、天国の彼女は幸せだったのだと、思うほかない。
最後にひとつだけ言及したい。安楽死を遂げた本人は幸せな最期を遂げたとしても、残された人たちは、患者が生前、抱いた思いを背負って生きなければならない。安楽死が認められた海外でさえ、その患者には本当に安楽死という道しかなかったのか、他の道を提示することができたのではないか、と家族は思い悩む。
本人が望もうとも、家族の合意がないまま、死を急ぐことは理想的ではない。ましてや医師がSNS上で計画し、死に至らせたことは、私は刑法に問われるべきものだと思っている。
今回のケースを「安楽死」と呼び、医師側の行為に正当性を見出そうとする人も出てくるだろう。だが安直に、日本で安楽死法制化の議論を始める前に、死を急ぐ社会の是非について、いま一度考える必要があるのではないだろうか。