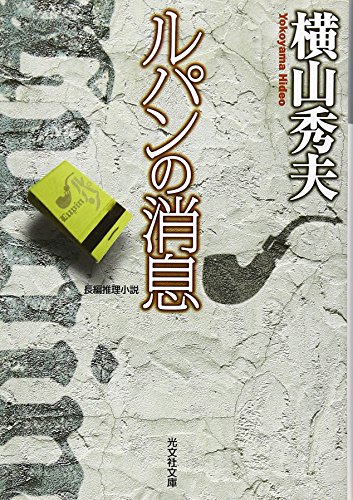新聞は人間の気持ちを描くには不向きなメディアだった
――日航機の墜落事故や功明ちゃん誘拐殺人事件も取材されたんですよね。
横山 ええ、どちらも忘れられない事案ですね。ただ12年間MAX状態で取材をしていましたから、大きな事件だから特別なことをやる、小さな事件だからやらない、ということはないわけですよ。1日は24時間、体はひとつ。それは変わりませんからね。そうは言っても、普通の事件なら社会面の隅に載るような特ダネが、事件が大きいと1面トップになったり、いつもは黙殺する大手紙が夕刊で派手に後追い記事を書いたりもする。なのでなんだか自分が大きな仕事をしているような錯覚に陥るんですね。記者同士が知り合うと、名刺代わりのように自分はどこそこの大きな現場を踏んだ、あの事件もこの事件も担当したというような話になるんですが、私はあまりしたくないですね。でも時代は変わりましたよ。今でも年に何度か後輩記者たちと会いますが、こんな特ダネを書いたなんて言いだす人は一人もいません。取材経験を自慢話のように口にするのは恥ずかしいことだと思う記者が増えているということでしょう。好ましいことですね。
――でも実際、横山さんは非常に優秀な事件記者だったそうですね。
横山 事件記者という意味では強かったです。最終的に強くなったというか。警察担当が長くなるにつれて、社内では事件記者をやるために生まれてきたような男だと思われていました。でも、そう言われれば言われるほど、自分の気持ちと齟齬が生じてきたんです。今も記者という職業に対する思い入れは深いですし、その記者職をまっとうできなかった敗北感を拭いきれていませんが、ともかく当時は次第に気持ちが離れていった。うまく説明できませんが、記者として「書く」ということと自分が考えていた「書く」が重なり合わないというか。一番大きかったのは、新聞ジャーナリズムは社会のシステムや事象を解析したり警鐘を鳴らしたりするには極めて有効でも、人間の気持ちを描くには不向きなメディアだと気づいたことでした。たとえば事件があって、関係者にインタビューしますよね。長くやっていると、相手が本音を言っているかそうでないかはわかりますよね。何かを誤魔化そうとしているなとか、こっちの期待に沿って喋っているなとか、ああ、この人は話した直後から迷いはじめているとか。それに人間は演技する生き物ですから、記者に名刺を出されたり、テレビカメラが回ったりすると、悲しいかな、本心とはかけ離れたことを口走ったりする。でも新聞的には相手が話した言葉こそが事実です。それを書くしかありません。もどかしいですよね。事実をいくら積み上げたところで真実にはならないわけですから。私自身、今こうしてインタビューに答えていますが、えー本当にそんなこと思っているの?なんて頭の隅からツッコミが入ったりしてますしね(笑)。
詰まるところ、事件事故をさんざんやったからこそ人間のほうに気持ちが傾斜したのだと思います。記者時代は分野を問わずノンフィクションを読みまくっていましたが、いつのころか、書いてある中身よりも、なぜこの人はこの本を書いたんだろう、のほうを考えながら読むようになっていましたから。
――それが小説を書き始めた大きな理由ですか。
横山 いくつもあった理由のひとつですね。一番はやはり会社のことでした。誰でも一度は離職を考えると言う、ちょうどその30代の前半で、なんとなくこの先会社で自分がどうなっていくのか見えてきた時期でした。そう遠くないうちに現場を外され、事件記者を束ねて指揮するような立場になるのだろう、と。そう考えたらへなへなと体の力が抜けました。もともと個人戦をしたくて記者になったわけですからね。実際にやってみれば記者職もチームプレーであり、団体戦に近いものでしたが、でも現場を離れたらもう本当に一生個人戦はできないぞ、とか思って。
で、夜中に小説を書き始めました。当時は県政担当に回っていたので時間が取れたんですね。もちろん夢は見ましたけど、本気で作家への転向を考えて書き出したわけではなく、まあ、この閉塞感をぶっ飛ばせ!みたいな感じでした。それが『ルパンの消息』ですね。ものすごく自由で、解き放たれた気分でした。書いていて楽しくて楽しくて、後にも先にも小説を書きながら楽しいなんて思ったのはあの時だけでした。
私にとってのビッグバンでしたね。当たり前のようにミステリーを選んだのは、やっぱり子供時代に読んだ中で一番面白かったからでしょう。書いているときは意識していませんでしたが、半分は警察を舞台にしていながら、明らかにリアリティより人間ドラマを優先させた書きっぷりです。「ザ・物語」というべきか、まさしくジャーナリズムへの決別の一打だったんですね。