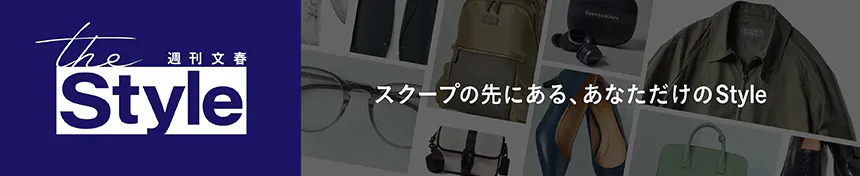広瀬すずが一見、自然にやってみせている演技に、彼女はどのように到達しているのだろう。
「違和感を感じた」「モヤがかかっていた」そんな当初の印象から、いかにして登場人物を具現化させたのか。彼女の言葉から、1つの映画が生まれてくる過程を探っていきたい。
◆◆◆
「これほど“違和感”を感じる物語もありませんでした」
『遠い山なみの光』に出演するきっかけは、石川慶監督からの手紙だった。
「そこに『これまでやったことのない、とても大きな題材に立ち向かっています』と書かれていたんです。監督は今までも大きな題材に取り組んでこられたのに、これ以上何があるのかと思ったんですが、本当に大きな題材で驚きました(笑)」
本作はカズオ・イシグロが初めて書いた長編小説の映画化だ。彼女が演じるのは長崎で原爆を経験し、戦後娘とともにイギリスへ渡った女性・悦子。正確には1980年代の悦子(吉田羊)が語る、1950年代の想い出の中の悦子である。
「正直なところ、これほどまでに違和感を感じる物語はなかったくらいの作品で……ただ、なんだか同じ船に乗ってみたいな、という気持ちになったんです」
その違和感は何に由来するものだろうか。
「私が演じた悦子は、家庭という居場所があるけれど、それだけでは自分が消えてしまうような孤独感があったんだと思うんです。そんななかで、外国に対する憧れという、ある意味ピュアな感情が、彼女を支えていたんじゃないでしょうか。一方で、お金に困っている佐知子さんを、若干下に見ているような部分も持っている。そんな脆さを抱えている人間なんです」
長崎で出会った佐知子(二階堂ふみ)は娘・万里子を抱え、苦しい生活を送っている。だが彼女は悦子に、付き合っている米兵とアメリカへ渡る希望を語る。
「でもアメリカなら、女だって何でもできると語る佐知子さんに、自分にはない強さを感じて、惹かれていったんだろうな、と」
だが80年代の悦子が、娘のニキ(カミラ・アイコ)に語る想い出話は少しずつ食い違いを見せていき、何が真実なのかわからない不穏な空気が物語を支配していく。これが、広瀬の感じた違和感の正体なのだろう。
「私自身もずっとモヤがかかっているような感覚で、どこへ向かって行けばいいんだろうと思っていました。たぶん、ほかのみなさんも同じだったんじゃないかと思います」