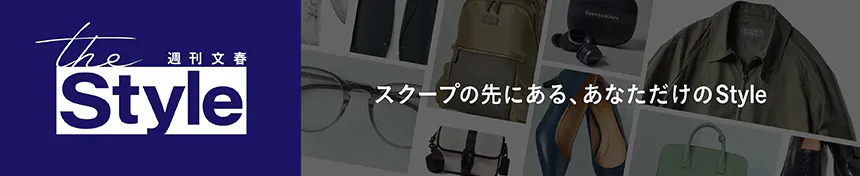絶縁状態にあった兄の突然の訃報から始まる4日間を描いた原作『兄の終い』を映画化した『兄を持ち運べるサイズに』。翻訳家・エッセイスト村井理子の実話に基づいた家族の物語だ。メガホンを取ったのは、『湯を沸かすほどの熱い愛』(16年)『浅田家!』(20年)など、これまでにいろいろな“家族”の姿を映し出してきた中野量太監督。幼い頃からマイペースで自分勝手な兄に振り回されてきた主人公・理子を演じた柴咲コウに、作品への想いを聞いた。
◆◆◆
原作者と自分の家族への思いが、私の中でマーブルになった
──本作のオファーを受けた時のお気持ちを教えてください。
柴咲コウ(以下、柴咲) はじめはポップな作品なのかと思っていました。でも、楽しみに脚本を読ませていただいたところ、思いっきり家族の物語で。中野監督が描く「等身大の家族」に対する想いに強く共感し、自分が持っている家族像と現実の家族について、あらためて考えさせられました。
私に兄はいませんが、母を早くに亡くしていることから、“身内を亡くした村井理子”という役を纏って動いている自分も、自然と想像ができました。
言語化して説明するのが難しいのですが、今回は「村井理子になるぞ」と意気込んで役作りをしたというよりも、ヌルッと理子になったと感じています。自分の家族への想いと、理子ちゃんの家族への想いが、私の中でマーブルになった、というか。もともと自分のなかにあった「家族に言いたいけど言えない気持ち」「言い過ぎて反省した記憶」を引っ張り出しながら、段々と理子になっていった気がします。
監督はニコニコしながら近づいてきて「もう一回」と言った
──中野量太監督とご一緒されるのは本作が初めてですよね。
柴咲 はい。プロフィールのお写真が「ニカッ」と弾けるような笑顔なので、太陽のような方なのだろうと想像していました。実際お会いしてみると、想像通り太陽のように明るくて正直で、表も裏もなく、全部顔に出てしまう方でした。
ほんのちょっとした表情の違いを狙って何度もカメラテストを重ねるのですが、ものすごく細かいところまでこだわりを持って撮影されるんです。こちらとしては“奇跡の一瞬”を逃してほしくないので、テストを少なくしてほしいと思いましたが、少し首をかしげながらニコニコ近づいてきて「もう一回」と言われるのが嫌でしたね(笑)。
──具体的にどんなシーンが大変でしたか?
柴咲 理子が昔を思い出して自分のスカートをぎゅっと掴むシーンです。少し子どもっぽい仕草で、「メディアにも登場する売れっ子翻訳家」という立場の中年の女性をどのように演じるよう求められているのか、監督の意向を探りながらいろいろやってみたのですが、微妙な手の角度にも監督ならではのこだわりがありました。手の位置や顔の表情など、本当に微妙に違うパターンを何通りも繰り返して、大変でした。