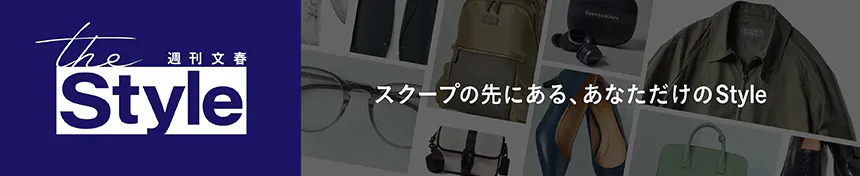東北地方の三陸沖で平成23(2011)年3月11日に発生した東日本大震災は、マグニチュード9.0と前代未聞の規模で、死者約1万5900人、行方不明者約2520人を出した。
火葬場だけでは遺体に対応できないと判断した厚生労働省は、3月14日、被災県に「特例火葬許可」を通達。「埋火葬許可証」がなくとも医師の死亡診断書や死亡検案書があれば、火葬や土葬が認められることになった。この埋葬の簡略化には、土葬の推進も含まれており、3月21日には東松島市内で自衛隊による土葬が始まったという。
ここでは、日本の火葬と弔いの歴史に迫ったジャーナリスト・伊藤博敏氏の著書『火葬秘史: 骨になるまで』(小学館)より一部を抜粋し、東日本大震災後に「仮埋葬」された遺体を掘り起こし、火葬を望む遺族の姿を紹介する。(全2回の1回目/2回目に続く)
◆◆◆
「仮埋葬」の遺体を掘り起こして火葬を望む遺族
墓にするわけではなく、遺体を入れた棺を土の中に埋めて一時的に保管し、数年後に火葬するのが「仮埋葬」である。その期間は約2年とされた。宮城県では東松島市のほか石巻市、山元町など6市町で仮埋葬が実施され、遺体数は2108体に達した。
だが、2年は持たなかった。「早く火葬してやりたい」と願う遺族が大半で、仮埋葬の数週間後には重機を持ち込んで、自力で棺を掘り起こす遺族が現れた。
かつて日本は土葬社会だった。縄文時代に遺体は、膝を折り手で抱えさせて家の近くに穴を掘って埋葬した。土壙墓への屈葬である。以降、地域や時代により形態は違うが葬法は土葬だった。
火葬が推奨された浄土真宗の信徒が多い北陸地方や、東京、大阪、京都などの都市部では江戸時代以降、火葬が増えていったものの、1940年代までは土葬が主で、高齢者の中には墓地まで葬列を組んで遺体を運ぶ「野辺送り」を経験した人もいる。
従って土葬は遠い昔の話ではない。にもかかわらず仮埋葬の遺体を掘り起こして、「弔いはお骨で」という遺族の思いは、葬儀は火葬を前提とする日本人の意識変化を示すものだった。それを実感したのは清月記(仙台市内の大手葬儀会社)の社員たちだ。