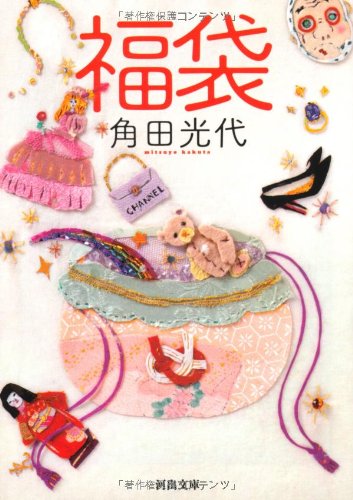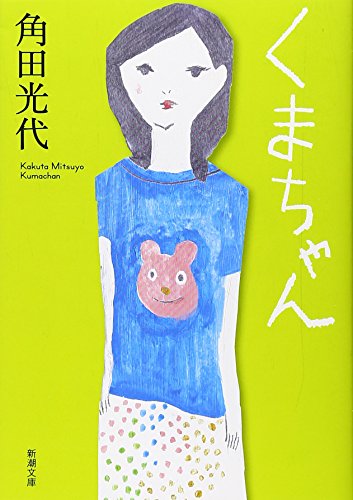強烈な関心に捉われた事件から想起した『森に眠る魚』
――いや、でも面白かったですもの。そこからまた短篇集時代になるんですよね。『三面記事小説』(07年刊/のち文春文庫)、『マザコン』(07年刊/のち集英社文庫)、『福袋』(08年刊/のち河出文庫)、『三月の招待状』(08年刊/のち集英社文庫)……。そして久々の長篇が『森に眠る魚』(08年刊/のち双葉文庫)。1人の母親がママ友だった相手の子供を殺してしまうという、実際にあった事件を思い出させますよね。
角田 私はあの事件が忘れられなくて、関連ノンフィクションは全部読んだんですね。なぜ自分があの事件の犯人にとらわれているのかがまるで分からないんですけれど、もうとにかく興味があって、知りたい、知りたい、知りたいと思って。で、その当時、松尾たいこさんが護国寺に住んでいたんです。遊びに行ったら一緒にいった編集者が私がその事件に興味があることを知っていて、ご近所ツアーをやってくれたんです。住んでいたマンションから護国寺から、裏のトイレから……全部回ってくれたんですよね。加害者の母親の住んでいたマンションと被害者の母親が住んでいたマンションを見た時には、なんか「うわー」みたいな気持ちがありました。
私のなかではそのツアーで終わるはずだったのが、編集者が「ほら連れていったじゃん」みたいな感じで(笑)、「連載してください」って言うので、「あ、そうか」と。それで始めたんですよね。あの事件とはオーバーラップするけれども、まあ参考にするというわけではなく、設定も違うふうにはしました。
――そうやって小説にしたことで、自分がなぜあの事件に惹きつけられるのかは分かりましたか。
角田 うーん。事件の本当のことはわかりませんが、私は勝手に女子高の感じと重ねたんだと思うんです。私自身が女子高出身で、嫌悪感もあるので、そのあたりを刺激された気がしますね。その世界を知っている、っていう。自分はそこから全力で逃げてきたけれど、もしも自分が母親になったら、あそこにまた自動的に戻るんだみたいな恐怖とか嫌悪とか、そういうのが刺激される事件だったんだと思うんです。
――たしかに、そうした心理が生々しかったです。それからほどなくして失恋が連鎖していく連作集『くまちゃん』(09年刊/のち新潮文庫)を出されている。本当にふり幅の広い方だなあと(笑)。次の長篇『ひそやかな花園』(10年刊/のち講談社文庫)は家族の話で、血のつながりがテーマになってくる。
角田 これは新聞連載だったんです。その頃に読んだ本に『ジーニアス・ファクトリー』というアメリカのノンフィクションがあって、優秀な人の精子を選んで天才を作ろうとしたら作れるのかというような、精子バンクビジネスの話だったんです。目の色は何色、背は何センチというのをチェックして精子を買える、というのを読んですごいなと思ったんですよね。その時にたまたまテレビで、自分が産めないから妹に産んでもらう、というような内容のドキュメンタリー番組をやっていたんですね。姉妹間で卵子をどうこうするという内容でした。その時、アメリカと日本の違いは何、って思ったんです。アメリカのこのドライな感じなものと、日本の絶対に自分の血が入っていないと嫌だという感覚の違いってなんだろうって。そこから、そういうことを小説にしていこうと考えました。
――科学技術の話でもあるから、また今までとは違う角田さんを読んだ気がしました。毎回小説を書く時に、これまでに書いていないものを書こう、などと意識されていますか。
角田 そうですね。自分のことを「課題派」と呼んでいるんですけれど、課題を常に与えて、それをクリアするように頑張っているんです。たとえば『坂の途中の家』だったら、意味合いをどうとでもとれるような会話を書けるようになる、とか。『八日目の蝉』でも、生活ばかり書いていると言われたから、生活の対極にあるものを書くということは考えていました。
――『ツリーハウス』(10年刊/のち文春文庫)は満州から始まる親子3代の長い時間にわたる話ですよね。あれを読んだ時に「あ、角田さんは大きい物語を書く方向に移ってきている」と思ったんです。過去を振り返って、自分の立ち位置を確認したいような気持ちが自分のなかにもあったので、しっくりきました。角田さんご自身は、どういう気持ちでこの物語を書こうと思ったのでしょうか。
角田 そうですね、年齢かなと思いますね。私が今いる場所、でなくて、その今に続くものが年齢的に見えてきたんだと思います。
さっきの生活と事件みたいに、「家族小説ばかり書く」とか「母と娘の話が多い」などと言われると、「じゃあぜんぜん違うものを書かねば」と思うことも多いです。自分に課したことがないのはミステリーとホラーですね。ホラーもいつか書けるようになりたいです。