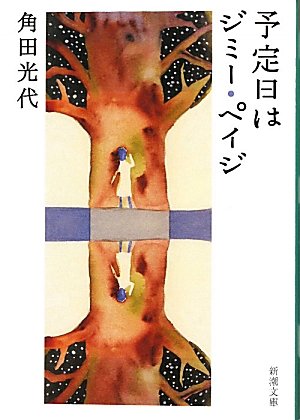『八日目の蝉』は逃げる話とまず決めて
――『Presents』(05年刊/のち双葉文庫)なんかも、人生のなかで受け取る贈り物がテーマでしたよね。最初のプレゼントは親からもらう名前、というのが素敵でした。……というように短篇をたくさん書くなかで出た長篇『八日目の蝉』(07年刊/のち中公文庫)は新境地とも言われ注目されました。どのようなきっかけで書かれたのでしょうか。
角田 あれは新聞小説でした。当時は短篇をいっぱい書いているなかで、評論家だったか編集者だったかに言われたのが、「生活ばかり書く」みたいなことだったんです。でも、生活を書くことには自分でも自信があったんですよね。でもそうか、生活ばかり書くって言われちゃったな、というので、生活じゃないものを書こう、じゃあ事件だ! となったんです(笑)。新聞小説ははじめてだったので、毎日みんなが読めるものを考えた時、逃げていけばみんな追いかけてくれるだろうと思いました。それで逃げる話というのを先に決めてから、なぜ逃げるのかを考えていったんです。
――まさに前半は、1人の女性が、自分を捨てた男の生まれたばかりの娘を連れて逃げる話。角田さんがサスペンスを書いた、ということでも注目されましたが、そうしたジャンルに挑んだ、というつもりではなかったんですね。
角田 違うんですよね。だから本が出来てきた時に帯に「サスペンス」って書いてあるのを見て、「これ怒られるからやめましょうよ」って言ったくらい(笑)。
――確かに後半は読み心地が変わりますよね。誘拐された赤ん坊が少女へと成長してからの話になりますから。私、当時雑誌の書評に後半がいかに素晴らしいかということを書いたら、その雑誌の編集者から「ネタバレだから書くな」と言われ、書き直させられました……。
角田 へええ。ネタバレとか、そういう話じゃないですよね。自分のなかでも、比重としても最後のほうが大きかったです。前半はやはり人が1人の人間に及ぼす影響の話でしかなく、後半のほうが、じゃあその子がどうやって生きていくのかという話ですから。
――その次に刊行されたのが短篇集の『ロック母』(07年刊/のち講談社文庫)なんですね。この表題作で川端康成文学賞を受賞されている。その後で、『八日目の蝉』の中央公論文芸賞受賞が決定するという。
角田 『ロック母』は寄せ集めなんです。92年から単行本にしてもらえなかったものたちを集めたんですよね。
――その次、『予定日はジミー・ペイジ』(07年刊/のち新潮文庫)は妊婦のお話ですが、これはすべて想像で書かれたという。でも当時みなさん、角田さんが妊娠したと勘違いしてましたよね(笑)。
角田 これも不思議な話で、新聞の1月1日に古井由吉さんと2人で短い新春小説を書くことになったんですね。「男は古井さん、女は角田さんで載せますから、原稿用紙3枚でお願いします」と言われて、じゃあ古井さんが絶対に書けないものにしようと思って(笑)。で『予定日はジミー・ペイジ』の最後の部分、産気づいてお父さんのことを思い出すという部分を書いたんです。古井さんに出産は書けないだろうと思って。
そしたら、その新聞が出た後に、すごいお花やお祝いのカードが本当に送られてきて。小説だと新聞には書いてあったのに、私が出産したと思った人が多かったんですね。そのなかで白水社の人がお手紙をくれたんです。「ご出産されたとは知りませんでした。その体験をぜひ書いてください」って。それで白水社の人に返事を出したんです。「すみません、産んでません」って(笑)。そうしたら「じゃあ、ここに至るまでの話を小説でいいので書いてほしい」となって、最後の3枚だけ新聞に掲載した短篇のままで、あと何百枚かはつけたしたんです。
――すごい話。
角田 ねえ。いろんな依頼のしかたがありますよね。私も断ればいいのにって、今説明しながら思いました(笑)。なんで「産んでないので書けません」って言わなかったんだろう。