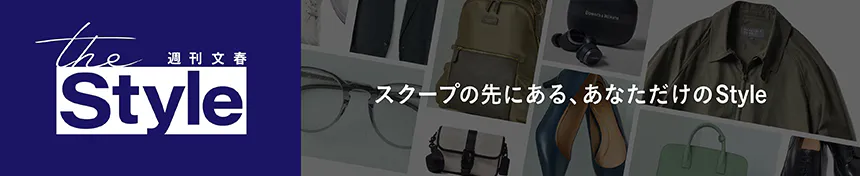平成のベストセラーとして異色の存在感を放つ『国民の歴史』。この一冊が刊行されてから20年。今なお議論されている「日本人としての誇り」「物語として歴史を語ること」を、著者の西尾幹二さんはどう考えているのか。聞き手は近現代史研究者の辻田真佐憲さんです。(全3回の1回目/#2、#3へ続く)
◆
なぜ『国民の歴史』は社会現象になったのか?
――西尾さんはニーチェを専門とする哲学研究者である一方、「新しい歴史教科書をつくる会」の会長を務めるなど言論人としての活動も多岐にわたります。今回はその歴史家としての独特の姿勢をお伺いしたいと思います。
西尾 私はドイツ文学者を名乗り、文芸評論家でもあって、「歴史家」と言われると少し困るのですが、今日はお話しすることを楽しみにしていました。どうぞ、聞いてください。
――現在も続く論争の一つに「歴史とは何か」があります。西尾さんは1999年、「歴史は物語である」との立場で『国民の歴史』を執筆されました。当時は「つくる会」の会長でもありましたね。それから20年。振り返ってみて、なぜあの本が72万部あまりのベストセラーになったと思われますか。
西尾 「国民国家」としての日本をもう一度見直そうという気運が高まっていた時期だった、ということが大きいと思います。自分で言うのも変ですが、あまりにも教科書的な歴史書、「日本は諸外国を後追いする国だった」「古代中国と近代西洋をモデルに仰いだ二義的周辺文明だった」とする日本通史しかなかったことに、人々が飽き飽きしていたこともあるでしょう。『国民の歴史』が一つの社会現象となっていることを実感したのは、それまで歴史に対して関心を持ってこなかった人から私に手紙が届いたときでしょうか。
――どんなお手紙だったのでしょう。
西尾 その方は病床でこの本を手に取ったそうですが、「全身を揺さぶられるような感動で、これは一体なんだと思い、読み出したらやめられなくなった。自分の人生が問われているように思った。術後に体力を回復した暁には、もう一回この本を読み直して、きちんと理解するんだ」とありました。こんな風に歴史書というより、喝を入れてくれる宗教書のように読む人が多数おられたように思います。その方とは今でも交流を続けています。
――長いお付き合いですね。
西尾 それからエンゼルス、マリナーズで活躍した大リーガーの長谷川滋利投手も“むさぼり読んだ”そうです。やはりアメリカに行ったらば、日本人であることを主張しなくては生きていけない局面もあると。そんな自覚をした時に、自分は歴史なんかを考えたことはなかったけれども、『国民の歴史』を読んで心を揺さぶられたのだそうです。これはテレビで語っておられたのをお聞きしました。