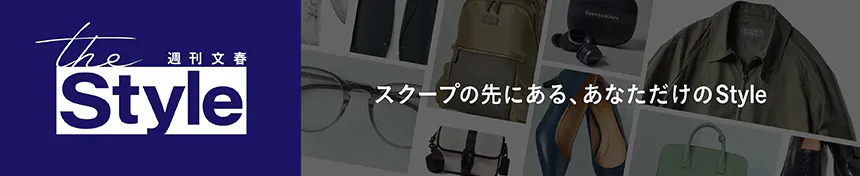今日一日を振り返り、私はどこにいただろうと考える。家で目を覚ました。電車の中にいた。コーヒーショップに、靴の修理屋に、駅前の薬局にいた。さあ、そこでは何が起こっていたか? 書くべきこと、話すべきことなど何も起こらなかったように思える。ところがひとたび本書を開けば、この生において見過ごしていい瞬間など一瞬たりとも存在しないのだ、という焦燥に近い想いに駆られる。平凡な日常のひとこまに、どれほど濃厚で複雑な生の気配が宿り得るか、目の当たりにして愕然とする。
タイトルが示すように、本書の語り手の「わたし」はあらゆる場所にいる。「歩道で」「待合室で」「美術館で」……簡潔に名づけられた短い断章が、四十六篇連なっている。彼女のいる場所に、ドラマチックな出来事は何も起こらない。歩道で誰かに声をかけられるわけでもなく、待合室で強盗に出くわしたりもせず、美術館で恋に落ちたりもしない。誰かと言葉は交わしても、深くかかわることはない。「わたし」はただ、そこにいるだけだ。とはいえ、人間が一人そこにいる、ということは、決して不動の状態を意味しない。むしろ彼女の内面は絶えず揺らいでいる。その揺らぎは時間の継ぎ目を綻ばせ、彼女をいくつもの過去の時間へと誘う。
「本屋で」という一篇で、彼女は別れた恋人と出くわす。そこで交わした素っ気ない会話をきっかけに、同棲時代から別れの顛末までの回想が始まる。ある人物と食事を取りに出かける場面で回想は幕を閉じるが、ほんの四ページに収斂されたエピソードの中に、何百ページぶんもの時間が折り畳まれている。そして二人がいまこの瞬間も、薄暗い路地を並んで歩いているような気がしてくる。不思議なことに、読むべき文章が消えた瞬間、終焉ではなく持続の感覚が強くもたらされるのだ。すべての章がそんなふうに終わるから、まるで同じ「わたし」がいくつもの場所にひとときに存在しているような感覚に陥る。ページが進むにつれて、彼女たちの影は色濃く重なり、その囁き声も未知の和音を奏でてより複雑に響きあう。
著者のジュンパ・ラヒリはベンガル人の両親のもとロンドンに生まれ、幼少期に米国に移住、家庭内で話されたベンガル語ではなく第二の言語の英語で小説を書き始めた。初期の短篇「病気の通訳」の、体の中を砂混じりの強い風がざっと吹き抜けるような独特の読後感は忘れがたい。本書はベンガル語でも英語でもなく、彼女が自らの意志で学んで習得したイタリア語で書かれた。書く言語が変わっても、ラヒリの紡ぐ文章からはいまもなおあの砂風が吹いている。同時に今作ではその風に、ひとが言葉を生み出そうとするその瞬間に湧き出る、不安、快楽、落胆、痛みをすべて含んだ生々しい呼吸が強く感じられ、息を呑む。
Jhumpa Lahiri/1967年、ロンドン生まれ。99年、「病気の通訳」でO・ヘンリー賞、『停電の夜に』でピュリッツァー賞受賞。2008年刊行の『見知らぬ場所』でフランク・オコナー国際短篇賞受賞。
あおやまななえ/1983年、埼玉県生まれ。作家。2007年「ひとり日和」で芥川賞、09年「かけら」で川端康成文学賞受賞。