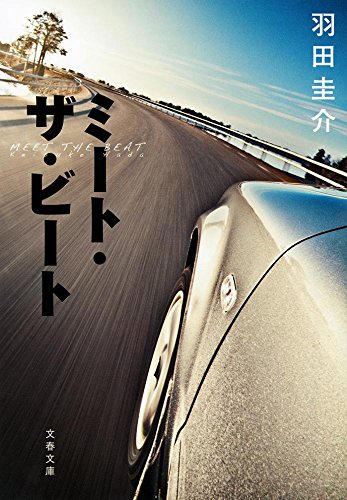背水の陣をしいて、会社員のうちにローンを組んでマンションを買い、会社を辞めて専業作家になった。
──さて、高校時代に小説を書き始めた羽田さんですが、『黒冷水』は3作目だったそうですね。これは兄の私物を覗き見る弟の話ですが、ずっと緊張感があるし、最後はびっくりする展開になるしで、面白かったですねえ。
羽田 1作目は自転車に乗る話を書き、2作目は校内暴力の話を書き、3作目に書いたのが『黒冷水』でした。でも、あれも自分が接してきた映画とか本を写経のようにして出しただけという感じがしますね。特別に勉強しなくても書けたというか。最後自宅で大騒ぎになるのも、山本文緒さんの『群青の夜の羽毛布』が映画化された時に、本上まなみさんファンだったので原作より先に映画で観て、自宅でわちゃわちゃする場面が頭に残っていたからです。主人公が学校のカウンセリングルームで自己客体化に努めるシーンなんかは「発掘! あるある大事典」でそんなようなことを特集していたからだし。わりとあの小説の大事な場面なのに(笑)。
――まさか、あの番組だったとは(笑)。『黒冷水』って、人が自分に見せていない部分、隠している部分を見ようとすることとか、その結果その人の違う部分が浮かび上がってくるところとか、その後の羽田さんの小説に繋がっていますよね。特に『隠し事』(12年刊/のち河出文庫)とか『盗まれた顔』(12年刊/のち幻冬舎文庫)あたり。
羽田 今書いている別の小説も、このデビュー作っぽい感じがあるんです。やっぱり誰にも頼まれていないのに書いた小説というのは、自分の核みたいな感じなんだなと思いますね。メタ的なものが好きだったりというところも。
――大学時代の単行本の刊行は少ないですが、書いていないわけではなかったそうですね。
羽田 「大学時代は遊んでいて2冊しか出しませんでした」とずっと答えていたんですけれど、結構ボツにしていたなと最近気づきました。原稿用紙500~600枚くらい書いてボツにしたりして。宗教団体とか右翼の話だったので内容的にどうかなと思ってボツにしたんですけれど。だから、その頃もすでに長篇は書いていたんですよね。それをボツにしたので最初に書いたものを引っ張り出してきて書き直したのが『走ル』(08年刊/のち河出文庫)でした。あ、その前に『不思議の国の男子』(06年刊/『不思議の国のペニス』を改題、のち河出文庫)も書きましたね。この年代に書けるものを書いたほうがいいのかな、と思って自分と同世代の男性主人公の話を書いていました。
――その頃は「こういう作家になっていこう」というのはありましたか。
羽田 特にないですね。自信満々ですからね。その時はなんだろう、作家にはもうなれたから、次はゴスペラーズに入りたいとか言っていたんじゃないですか(笑)。20歳前後の頃はR&Bシンガーになりたいと思っていたんですよ。小説については、もう努力しなくても有名になれると思っていました。そうではなかったということをその後数年間で知るんですけれども。
――では卒業後、なぜ就職したんですか。
羽田 就職するほうが面倒くさくなかった。中学から明治大学の付属校に通わせてもらっていたのに、学歴が関係ない専業作家になるのもわけわかんないなと思って。自分にとっては就職したほうが親に面倒な説明しなくていいし楽だったんです。それに周囲が流行り事のように就活を始めていたので、自分も応募しようと思って。
――その就活体験がのちに『「ワタクシハ」』(11年刊/のち講談社文庫)に繋がっていくんですね。
羽田 そうですね。就活を始めた瞬間から、あ、これ小説にしようと思いました。小説にするつもりで就活していました。それで1年半だけ、会社勤めをしました。
――その体験は『ミート・ザ・ビート』(10年刊/のち文春文庫)に活かされていますか。
羽田 どうなんでしょうかね。会社は辛くはなかったんです。不満はなかったんですけれど、入社後3か月くらいは真面目に朝早く起きて小説を書いたりしていたのに、会社の仕事の肩の力の抜き方を分かってくると小説も力を抜くようになって、書かなくなっていって。読書量も減って、ひどいことになったんですよ。
それで軽い気持ちで背水の陣をしくことにして、会社員のうちにローンを組んでマンションを買って、会社を辞めて専業作家になりました。『ミート・ザ・ビート』は会社員だったうちに書いて、『御不浄バトル』(10年刊/のち集英社文庫)は辞めてから続きを書いたのかな。『「ワタクシハ」』も会社員時代に書きかけていたものを後から形にしたんでした。で、その後が結構、停滞というか。何をやったらいいんだろうという感じになって。