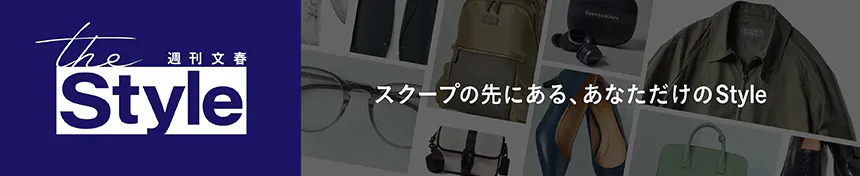近づいて見ると野添だった。「よくやった。よく見つけてくれた、本当にご苦労様でした」と慰労するつもりで肩に手をかけた。
野添は大粒の涙を流して男泣きしている。野添には、2人の娘がいて、年の頃もルーシーと同じなのだという。
「ルーシーが呼んでいたんだな……」
有働は、初めて胸が締めつけられる思いを感じ、涙が滲んだ。
洞窟の中には、遺体が放つ臭気が…
発掘作業は夕刻までには終了したが、鑑識課員は、狭い洞窟で窮屈な姿勢を強いられながらも作業を続けた。外から見られないよう青いビニールシートで洞窟全体を覆ったことから、換気状態が悪く、その上さらに照明がたかれ、遺体が放つ臭気と濁った空気が澱んで、最悪な状態だった。ベテランの鑑識課員はともかく、現状保存に当たった捜査員たちは、防臭マスクを着けなければ息もできないほどだった。
「最後になってルーシーさんが助けてくれた」
捜査員たちはそう言いながら、それぞれ線香を上げ、黙禱を捧げてから現場を後にした。
阿部以下、捜索隊は周辺を片付け、見張り役2名を残して「D荘」に帰った。
宿の人たちが、阿部たちを出迎えて声をかけてくる。
「やっと見つかったんですね。ご苦労様でした」
どうやら夕方のニュースで遺体発見の事実を知ったらしい。
最後の宿泊。食卓には、女将の心づくしの大きな船盛りが置かれていた。
ルーシーのものと思われる惨たらしい遺体は、麻布警察署の車庫にいったん運ばれた。村岡光鑑識課長、久保正行鑑識理事官、有働理事官らが見守る中、鑑識課員が白いビニール袋を開けていく。
「空気に触れたら最後、顔が崩れてしまう」
両腕、両足、両足首、胴体、頭部と合計8つに切断されていた遺体は、湿った砂の中に埋められていたためか腐敗はそれほど酷くなく、ほぼ死蠟化し、白い石鹼のような状態になっていた。しかし、その臭気にはその場の全員が顔を顰めた。
頭部はセメントを被せるように塗り固められていたが、塗りは薄く、顔は十分に識別できた。
鑑識課員が鉈のようなものを頭部に当て、その背に金槌を振り下ろして割ろうとした時、傍らの有働が静かに声をかけた。
「割った瞬間に写真を撮れ。空気に触れたら最後、顔が崩れてしまう」
頷いた鑑識課員は、細心の注意を払って金槌を振り下ろした。一瞬にフラッシュが光り、セメントに覆われた顔が光の中に浮かぶ。
「ルーシーだ……」
生前のルーシーの写真が頭にある誰もが口々に言った。
後日、ルーシーの両親から渡された爪と遺体の皮膚とをDNA鑑定した結果、発掘された遺体は紛れもなく、ルーシー・ジェーン・ブラックマンのものだと断定された。
その他の写真はこちらよりぜひご覧ください。