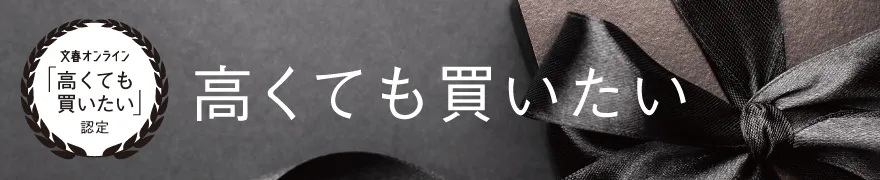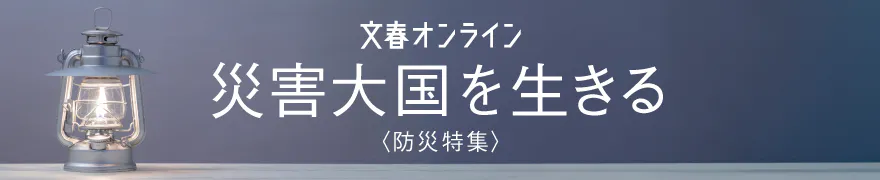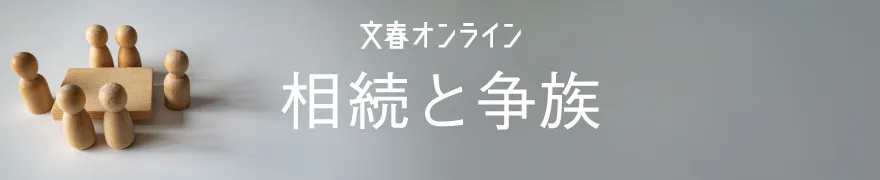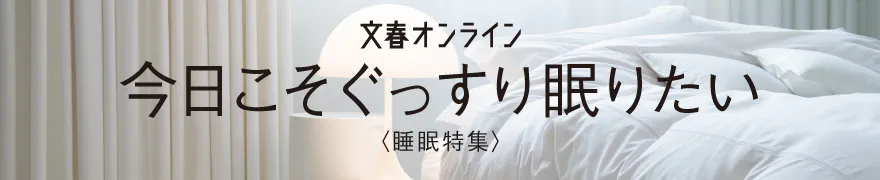その後まもなく面会交流支援を卒業。今ではLINEやメールで夫と直接やり取りをし、面会交流の回数や時間も拡大。離婚は成立したが、クリスマスなどには元夫婦で息子を囲み、一緒にパーティーができるまでになった。
「この3年でここまで来るなんて、自分でもほんとに驚きです」とTさんは話す。
離婚後の関係をサポートする法や制度の整備を
筆者はこれまで多くの別居・離婚後の親子を取材してきた。「子どもに会えない」「会わせられない」という人たちの背景や理由はさまざまだし、「別れた夫婦が共に子育てに関わるなんて無理」との言葉も多く聞いてきた。家庭内暴力や虐待など、被害者の厳格な保護が必要な場合もある。
だがその一方で、Tさんのように適切なサポートがあれば、別れても双方の親が子どもの養育に関わり続けられるケースも少なくないのではないか、と痛感することも多かった。
共同養育支援に取り組む一般社団法人「りむすび」のしばはし聡子代表は、「離婚のこじれの原因の9割は感情」と指摘する。「離婚の条件を決める前にカウンセリングで感情を整理し、夫婦間のわだかまりを解消すれば、親同士の関係を再構築しやすくなり、最終的に共同養育をできる関係性になる方も多い」と話す。
Tさんにも別居・離婚時に何が必要と思うか、聞いてみた。「私にとっては特に、客観的な立場の第三者に話を聞いてもらうこと、カウンセリングなどの支援でした」とTさん。加えて「離婚後の親子関係に関する知識や、安心して話し合える、話し合わなければならない場や制度、子どもの養育計画の作成義務化など親としての責任を果たすための仕組み」とも。いずれも離婚後の共同監護制度を導入する欧米などでは整備が進んでいるものの、日本では公的支援としてほぼないものばかりだ。
また、日本で導入に関し議論が続く、離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」については賛成派というTさん。「共同親権制度があるのとないのとでは、別居・離婚時の情報の整理の仕方が違ったと思います。一方の親しか親権を持てない今の状況では、親権を取るか取られるかしかなくて怖かったし、その恐怖の中で極端な思考になっていった面はあると思います」