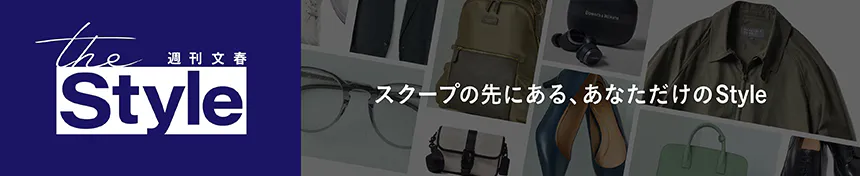公式YouTube、ファンクラブイベント、ラジオ出演や声優業など、ここ1年ほどで表舞台に姿を見せる機会が急増している中森明菜。きょう7月13日で60歳の誕生日を迎えた彼女のこれまでの歩みとはどのようなものだったのか。
歌手志望だった母のもとに育ち、1982年にデビューを果たした彼女が、時代を象徴するアーティストへと登り詰めるまでの日々を振り返る。(全3回の2回目/続きを読む)
◇◇◇
新人時代の中森明菜については「マネージャーを怒鳴り散らし、次々とクビにする」などといった噂が広まり、業界では「生意気」「わがまま」といった評判もつきまとった。しかし、そこには彼女なりに理由があった。
たとえば、当時の雑誌取材では女性アイドルに対し下着の色を訊くなど、いまならセクハラでしかない質問がまかりとおっていた。これに明菜は「私は歌手です。どうしてそんな質問をするんですか?」と食ってかかり、マネージャーにもどうしてあんな質問をする取材にOKを出したのかと問いただしたという(『週刊現代』1988年12月17日号)。
アイドルとして“異質の存在”だった
アイドルといえば、大人に従順で口答えなどけっしてしないというイメージがあったなかで、明菜はあきらかに異質だった。デビュー当時の女性誌の記事でも、大手芸能事務所(彼女の所属した研音ではない)のマネージャーが《明菜はあまりにも正直な子です。それが、体質の古い芸能界では異質なものに見えることが多いんですよ》とコメントしている(『女性セブン』1982年12月16・23日号)。
のちに明菜自身が語ったところでは、彼女はデビューした瞬間から「歌手・中森明菜」をつくらなくてはいけないと思い、自ら「プロデューサー・中森明菜」として理想の歌手像を模索してきた。しかし、この感覚は他人には理解しがたく、さんざん誤解も受けたという。
《たとえば「中森はこういうふうに売っていきたいので、そういう番組に出るのはよくないです」と言うとします。スタッフが言えば、それは方向性だし、明日に向けての売り方の戦略だし、会議で話されてしかるべき内容でしょう。そういうスタンスで客観的に物を言っているつもりなのに、「この番組は嫌い」と感情で言ってるととられてしまう。私はあくまでプロデューサーの立場で、歌手・中森明菜のために言ってるつもりなのに、単なるワガママだと思われてしまう。だったら他の人がちゃんと私をプロデュースしてくれるかといったら、誰もしてくれない。だから自分で自分の方向性を切り開いていくしかなかったんです》(『婦人公論』1999年5月22日号)