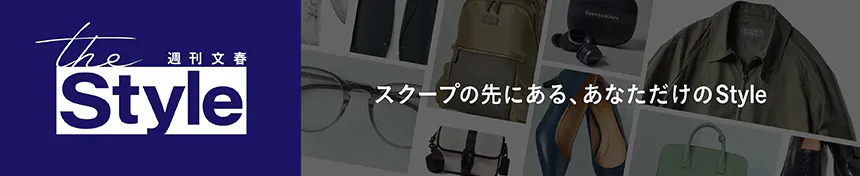カフカ研究で知られる文学紹介者の頭木弘樹氏が新著『痛いところから見えるもの』で挑んだテーマは、「痛み」。誰もが経験する根源的な感覚でありながら、その本質は他者に理解されにくく、ときに当事者を深い孤独へと追いやってしまう。潰瘍性大腸炎から腸閉塞まで、長年、つらい病と共に生きてきた著者が語る、文学だからこそ可能な「痛み」へのアプローチとは?
◆◆◆◆
痛みは切実なのに、言語化がとても難しい
――今回、なぜ「痛み」というテーマに向き合おうと思ったのでしょうか。
頭木 痛みは生きていくうえで誰もが経験するものですが、一方でとても個人的なものです。どう痛いのか、当人にしかわからない。でも、周りにわかってもらえないと孤独ですし、生活していく上でも困ります。医者にきちんと伝えられなければ、それこそ命にも関わることもあります。それほど切実なテーマなのに、言語化がとても難しい。美味しい料理の話とかと違って、人が喜んで聞いてくれる話でもありません。
痛む当人と、そばにいる家族や親しい人が、互いにわかってほしい、わかってあげたいと思っていても、うまく伝わらない。そのもどかしさに、ときには腹が立ってしまうことさえ。そんなとき、両者のあいだに、一冊の本があったらどうだろうと思ったんです。本のどこかのページを指し示して「こんなふうに痛い」と説明したり、「こんなふうに痛いの?」と質問したりできるような、そういう本があったらいいな、と思ったのが執筆のきっかけです。
――痛みという症状には、独特の厄介さがあるように感じます。
頭木 ほんとにそうですね。激しい痛みを経験した当人でさえ、いったん治まってしまうと、その感覚を自分の内に完全には再現できないんですよね。生きていくために、痛みを忘れるようにできているのかもしれませんね。その一方で、トラウマのように強く残ってしまう“痛みの記憶”もあります。忘れるのも、忘れられなくなるのも、自分の思うようにはなりません。
慢性痛も大きな問題です。とくに体としてはもう治っているはずなのに痛みが残ってしまう場合、かつては「心因性」や「思い込み」で片付けられていましたが、今は脳がリアルに痛みを感じ続けていることがわかってきています。脳のイメージと実際の体が乖離すれば、切断したはずの脚が痛むような「幻肢痛」が生じたりもします。
潰瘍性大腸炎で壁をかきむしるような苦しみに……
――頭木さんが大学生のときに発症した潰瘍性大腸炎は、やはり相当な痛みでしたか?
頭木 潰瘍性大腸炎は痛みが強いほうの病気ではありませんが、炎症を重症化させてしまったので、かなり痛かったです。自分の大腸がどこにあるのかわかりましたね。血便が続いて、熱も出ていたので、私は朦朧としていたのですが、壁をかきむしって苦しんだりしていたそうです。
大腸の内視鏡検査も、僕の場合、腸がかなり弱っているため、痛くて。しかも、これまで経験したことのない種類の痛みで……。痛みにも種類があって、たえにくいものがあるということを知りました。痛がらないと「穿孔」といって腸を突き破ってしまうリスクがあるので、麻酔をかけられないんです。