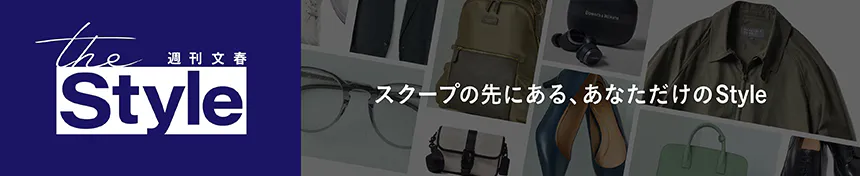日本を代表する歌人でありながら、エッセイや評論の分野でも活躍している穂村弘さん。この度刊行された書籍『満月が欠けている ―不治の病・緑内障になって歌人が考えたこと―』は、「ライフストーリー」について語った一冊だ。
「書名の『満月』は視野のことなんです。眼科で視野を測ると、見えている部分を表す白い満月の円の中に、全員が持つ盲点とは別に、病気のせいで見えていない部分の黒い欠けができる」
緑内障を公表してから20年。だが、普段馴染みのない医学系の出版社からの依頼に戸惑ったという。
「これまでもエッセイとかで持病のことは書いていたけど、一冊出すほど書くことないなって。でも、編集者に会って『目』についての思い出話をしていたら、話がたくさん出てきて。自伝みたいな形ならまとめられるのかなと思った」
子供の頃から目が悪かったという穂村さん。「目」に関してのエピソードはたくさんあるそうだ。
「小学1年生の頃からメガネをかけていて、付けられたあだ名は『メガネザル』でした。あと、当時引っ越しが多くて、父の転勤のせいだと思っていたら、母が占い師に『引っ越さないとお子さんの目は良くなりませんよ』と言われたのを信じていたんだとわかった」
本書では、穂村さんやご家族の「目」の話のほかに、医師との2つの対談や、様々な人物による「瞳を巡る短歌」が紹介されている。
1つ目の対談「今日は患者の君の目を診る」の相手は、穂村さんの緑内障治療の主治医・後藤克博さん。
「私が病気を告知されたとき、タイトルに『緑内障』とある本を何冊も買い込んだ。同じように患者さんが読むかもしれないから、素人目線だけでなく、専門家に治療の話をちゃんと教えてもらった方がいいと思って、お願いしたんです」
緑内障を告知されてからしばらくの間、強烈な不安を感じていたという。
「寝る前に、『次の朝、目が覚めたら目が見えなくなっているんじゃないか』と思ってた。眠りというのは一種の死のメタファー。『明日の朝、目が覚める保証がない』という感覚も年を取るほど増すはず」
病気を機に、死を意識する機会が増えた。2つ目の対談では、精神科医の春日武彦さんと「生と死」について語り合った。
「春日先生は元々産婦人科医だったから、人が生まれるところも死ぬところもいっぱい見てる。聞いて納得したのは、ドラマみたいに『ご臨終です』って遺族に伝えるのにはかなり勇気がいるってこと。生は死に関連していて、オンオフで簡単に確定しないんです」
死というものは生命に限った話ではなく、いろいろな形があるという。その例を歌人らしい言葉で語る。
「短歌には生と死がキメラ状に出てくるんです。例えば、恋人だった人が友達になると、もうメガネを外した顔を近くで見ることはない。これは自分の中に『メガネを外したあなた』が存在しなくなるという一種の死。他にも、親がボケて自分のことがわからなくなったら、親は生きてるけど『何か』は死んでる。そういった死の匂いが混ざってくると短歌は面白くなる」
本書では「生と死」をはじめ、「弱さ」や「シンパシー」といった、これまで歌人としても向き合ってきたテーマを掘り下げた。
「病気という題材は重いからデフォルメしにくい。一生治らない病気だからなおさら。その上で、同じ病気の人が混乱しないで読めるように、自分自身のそのままのことを語りました」
ほむらひろし/1962年、北海道札幌市生まれ。歌人。90年『シンジケート』でデビュー。2008年『短歌の友人』で伊藤整文学賞受賞。18年『水中翼船炎上中』で若山牧水賞を受賞。歌集、エッセイ集以外にも著書多数。