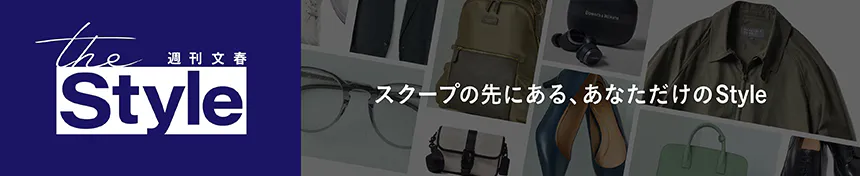『一色一生』などの著書で名随筆家としても知られる101歳、紬織(つむぎおり)の人間国宝・志村ふくみさん。「手仕事なくしては、一日も生きられない」という志村さんが70代の頃に綴った随筆『母なる色』が今月、オリジナル写真を多数加えて文庫で刊行された。AI時代の到来といわれる今だからこそ輝きを増す名著の魅力を、小説『まぼろしを織る』で染織をテーマにした著書を持つ作家・ほしおさなえさんが紹介する。
★★★
草木染めと機織りを体験して
色というのは不思議なものである。志村ふくみ先生の文章を読んでいると、色というものがものの表面にある装飾ではなく、ある種の生き物のように思えてくる。
数年前、成城学園前にある「アトリエシムラ」に通ったことがある(現在は祖師ヶ谷大蔵に移転)。ふくみ先生の芸術精神を継承する染織ブランドのギャラリーで、先生の教えを受けた人たちがワークショップを開いている。そこで数回草木染めと機織りを体験し、半年かけて帯を織った。
わたしはふくみ先生と直接お目にかかったことはないが、そのようなわけで心の中ではいつも「先生」と呼んでいる。まさに「先に生きた人」であり、ある道を拓かれた人、人を導く人であるということにもよるのだと思う。
自然の色と、人工の色
着物には「染めの着物」と「織りの着物」がある。織った布を染めたのが染めの着物。染めた糸を織るのが織りの着物だ。織りの着物では、染めた糸を組み合わせることで模様を作る。屑繭からとった手紡ぎの絹糸を使った織りの着物を紬と呼び、本来は庶民の着物であった。
ふくみ先生は、この紬の着物を芸術の域に高めた人である。草木染めや藍染めといった天然の染料で染めた何色もの糸を組み合わせて織られた作品は、着物そのものが命を持っているかのようで、見ていると胸の奥がざわざわする。
ワークショップで何度か草木染めを体験した。植物の根や枝や実を煮出し、熱い液に浸して糸を染める。植物から想像できる色になることもあるが、外見からは想像できない色になるものもある。色が糸にはいるのには時間がかかり、何度も染液のなかで糸を手繰る。だんだんと染まっていくそのあいだにも、色というものの不思議を感じる。
昨今は、服飾品も印刷物も人工の色で彩られている。印刷物ならCMYKの数値を変えればどんな色でも生み出すことができる。しかしそこに見える色は実は擬似的なもので、拡大すると4色の点の集合になる。人の目がそれを色と認識しているだけだ。そもそも自然の中にある色も人の目にそう映っているだけで、ほかの動物にはまた別の世界に見えていると聞いたことがある。絶対的な「色」というものはこの世に存在しないのかもしれない。
しかしワークショップで糸を染めるうちに、ここで糸にはいってくる色は、そのような色とは本質的に異なるものであるような気がした。確実に、液体から糸になにかが移動してくる。液体に溶けているなにかを糸が吸いあげていくのだ。