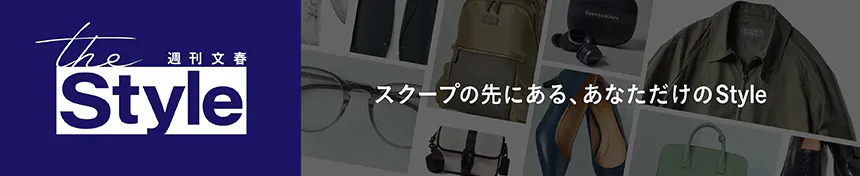直木賞に続き、読書メーター OF THE YEAR、未来屋小説大賞、「あの本、読みました?大賞」など数々の賞へのノミネートが引きも切らない『踊りつかれて』。デビュー作『盤上のアルファ』から15年にわたり塩田武士さんへのインタビューを重ね、作品を追い続けてきた吉田大助さんが、デビューから最新作『踊りつかれて』に至るまでの軌跡を辿ります。(後編/前編はこちら)
◆◆◆
社会派ミステリーから社会派小説へ
ブレイク作となった『罪の声』から最新長編『踊りつかれて』へと至る作家の道のりを俯瞰してみた時に、キーとなる作品が2つある。1つ目は『歪んだ波紋』(2018年刊、現在は講談社文庫)だ。著者のキャリア史上唯一の短編集である本作は、のちに第40回吉川英治文学新人賞を受賞する。
ジャーナリズムの世界を舞台にした、5つの物語が収録されている。5人の主人公はいわゆるレガシー・メディア(新聞やテレビ)の関係者であり、誤った情報を公のものとしないよう細心の注意を払っている。だが、落とし穴は突然足元に現れる。自分は間違ってしまった、そう気付いた時、その事実と真摯に向き合う者もいれば、「認めたくない。黙ってスルーしたい」といった感情に支配される者もいる。「誤報」にこそジャーナリズムに関わる人間の個性や本質が現れる、という着眼が素晴らしい。
ミステリー作家としての力量を存分に発揮した作品としても記憶に残る本作は、レガシー・メディアという言葉をあえて頻用することで、現代の情報環境の変化を際立たせることにも成功している。レガシー・メディアは誤報を起こさないことを重視するが、ウェブニュースサイトなどネット発の新興メディアはともすればそれを軽視し、フェイクニュースの産出に積極的に加担する。ある登場人物は言う。「情報に対する考え方が根本的に変わってきているのかもしれません。正しく、人の役に立つニュースが前提やと思ってきたけど、正しいより面白い、人の役より自分の役に立つ、そんな情報が飛び交う世の中になっても不思議じゃない」。この一文が印字されてから約7年後、情報環境の変化に著者が全く異なるアプローチで向き合った作品が、『踊りつかれて』だった。
第9回渡辺淳一文学賞を受賞した『存在のすべてを』(2023、朝日新聞出版)についても触れておかなければならない。50ページものボリュームを割いた「序章――誘拐――」で描かれるのは、平成3(1991)年に神奈川県下の全く異なるエリアで発生した「二児同時誘拐」だ。誘拐事件が同時に発生したことで捜査体制はガタガタになってしまい、1件目こそ無傷での人質解放となったが、2件目は警察の判断や不運が重なって犯人を取り逃し、資産家の孫の男の子は帰ってこなかった。ところが、序章の最後で驚くべき一文が現れる。〈澄んだ夜空の下に舞い降りたのは、7歳に成長した自分の孫だった〉。3年もの長きにわたり帰ってこなかった男児が、祖父母の家のドアを叩いたのだ。
物語はそこから、「犯人当て」の方向へは進まない。本編が始まってすぐに、あっさりと犯人が割れる。誘拐された男児の3年間の空白に何があったのか? これこそが本作において解かれるべき「謎」なのだ。そして、この「謎」の真相を追究していく過程で、30年前の誘拐事件によって強制的に運命を変えられた人々、その周りにいた人々の人生が稠密に記録されていく。
上記のような流れの先に、『踊りつかれて』が現れる。まず読者が目にすることになるのは、「宣戦布告」と題された文章だ。ブログに投稿されたその文章で、書き手の「俺」はかつて愛した芸能人が2人いたと告白する。不倫スキャンダルがSNSの餌食となり、自殺した令和のお笑い芸人・天童ショージ。バブル期に一世を風靡しながら、暴言テープの流出により90年代半ばから姿を消した昭和の歌姫・奥田美月。「二人とも週刊誌とおまえらに抹殺されてしまった」。匿名で記事を書く週刊誌関係者や誹謗中傷を繰り返す一般人に、ケジメをつけてもらうことにしたと「俺」は記す。「これから重罪認定した八十三人の氏名、年齢、住所、会社、学校、判明した個人情報の全てを公開していく」。