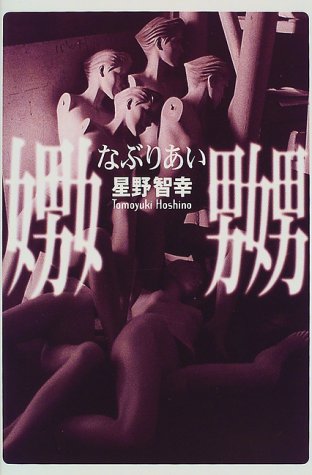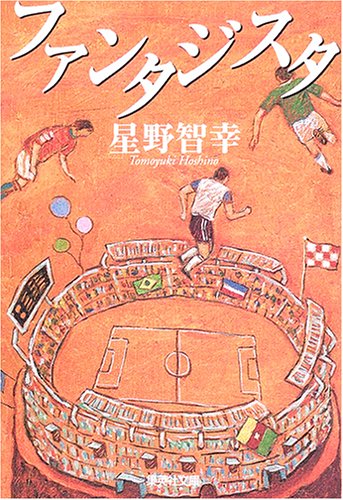――では、次の『目覚めよと人魚は歌う』(00年刊/のち新潮文庫)はいかがでしょう。これは三島由紀夫賞を受賞されましたね。
星野 愛知県で日系ブラジル人の少年が抗争で殺されてしまうという事件が実際にあったんですね。それをモチーフとして、ブラジル人をペルー人に置き換えて書きました。
90年代はブラジルやペルーの日系人を中心に、ラテンアメリカからいっぱい人が来ていたんですね。その時に、日本はラテン化しうるんじゃないかと僕はすごく期待をしたんですが(笑)、実際にはラテン系の人は日本社会のマジョリティからは微妙な線を引かれて、ラテン系のコミュニティの中で生きるしかない人が多かったんですよね。その中で事件が起こった。そうやって線を引いて住み分けるというか、ある種の排除してしまうメンタリティを崩すような小説を書きたかったというのがあります。
その一方で、差別や暴力を受けた側の日系ペルー人の一部が先鋭化していく。そこでもやっぱり先鋭化の暴力の問題をすごく考えたんですけれども、そうすると結局、両者同じような立場で差別、排除の応酬をしているだけになってしまう。主人公はその先鋭化が醸し出す「正義の怒り」の魅力に惹かれながら、でもそれはまずいんじゃないかと思い、別の道を探そうとするんです。
――『毒身温泉』(02年刊)は文庫化で『毒身』(講談社文庫)にタイトルが変わりましたね。これは独身の人を集めた下宿など、単身者や共同体についての話です。『嫐嬲』もそうですけれど、一般的な家庭を作るのではなく、また違う生き方もあるんじゃないかと提示してくれている。
星野 これは『嫐嬲』の延長で出てきた作品で、ジェンダーだけでなくて家族の問題を扱っています。一般的な家族像、家族の中での役割みたいな考え方を崩したかった。当時、結婚しない人が急増し始めたり、あるいは結婚する年齢がすごく上がってたり、また離婚も普通になったりと、変化が目立ってきたころでした。
いわゆる核家族的な家族像を標準としている限り、自分は普通じゃないという劣等感を抱かされる人は増える一方でした。そうじゃない生き方もライフスタイルとしてありなんだと肯定できるようにしていかないと、社会が立ち行かない。その新しいモデルケースを探りたかったんです。だから語り手も、一読しただけでは男か女か分からないようにしました。そうしたら読者から「いつまで経ってもこいつ、男か女か分からない」という文句が結構きたんですけれど(笑)。それをあえてやったわけですが。
――次の『ファンタジスタ』(03年刊/のち集英社文庫)は野間文芸新人賞を受賞しました。この表題作は、もうすぐ国民投票で首相に選出されるだろう男性と、とあるカップルの話ですが、星野さんのサッカー好きがよく分かるという。
星野 そうですね、サッカーでいつか小説を書きたいなとは思っていました。首相公選制が実現した世の中の話でもあるので、サッカーと選挙、サッカーと政治がテーマともいえますね。確か、2002年のワールドカップの頃に書いている。あの年のワールドカップは、渋谷のスクランブル交差点でハイタッチする、なんてことが始まった瞬間でしたよね。あの熱狂が、『ファンタジスタ』で描かれるモチーフのひとつです。なにしろ自分がサッカーで熱狂すると、歓喜のなかで自我を吹っ飛ばしたいとか思っちゃう人間なので(笑)。そういうものに嫌悪をおぼえるということと、両方同時に盛り込みました。
もうひとつモチーフにしたのは、当時の小泉首相ですね。彼は歴代の首相とは一転して、カリスマ的な人気を誇った。その時に、ひとつの言葉やひとつの単語や非常に明快なひとつの表現にみんなが熱狂して、それでもう何かを理解したような気になる、ということが加速したと思います。
さらにはあの時に「改革」という言葉もすごく言われていましたが、内容はよく分からないのに本当に変革を実施している、自分もそれに加わっているという意識がみんなのなかに芽生え、共有した。政治でそういうことが起きた、すごく久しぶりの時間だったと思います。
それを「ファンタジスタ」では、小泉首相みたいな人のさらに3人くらい後に出てきそうな、より若くてよりカリスマ性を持っていて、よりみんなが共感するだろうヴィジョンや正しさを語る人間として作ったんですよね。だけれど、そのレトリックの中にいろんないかがわしさがあるので、ある種のリテラシーを持たないと、そのいかがわしさをちゃんと読み取れない。そういう言葉の使い手として描きました。