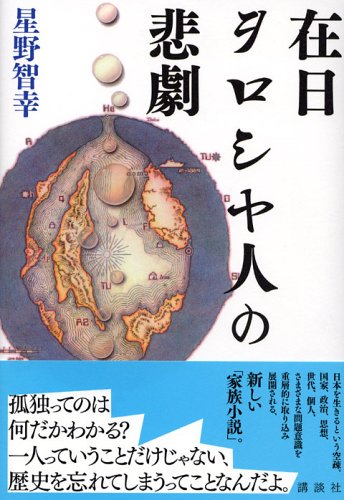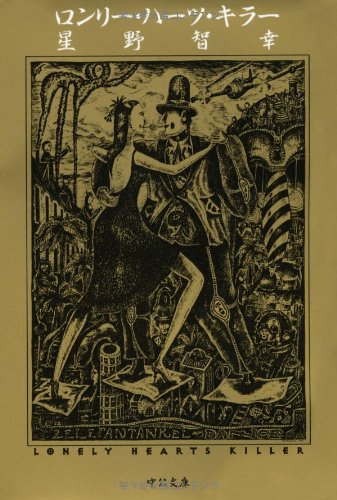自ら「政治小説」と銘打って書いた『ロンリー・ハーツ・キラー』
――ウラワ・レッヅの会長の長田という男性が、首相候補なんですよね。
星野 そうです。長田は現役時代には世界的選手として活躍したんですけれど、その所属チームとして僕が選んだのが、当時イギリスで2部リーグ落ちしていたマンチェスター・シティだったんですよね。僕は自分で先見の明があったなと自分を褒めているんですけれど(笑)、その後マンチェスター・シティはタイの元首相のタクシンが買い取ってから突然大金持ちになって、今はもうヨーロッパの強豪サッカーチームに復活しました。もともと名門のチームで、アジアマネーに買い取られて強豪として復活しうるチームとして僕が考えたのがマンチェスター・シティだったんですが、その通りになったんです(笑)。
――作中で予言していたようなものですね(笑)。ところでその後の『在日ヲロシヤ人の悲劇』(05年刊)の首相の名前が長田ですが、同一人物ですか。
星野 う、また見抜かれた(笑)。まったく同一人物にしたかどうかは忘れましたが、とりあえずあの人物を彷彿させる、共通した要素を持つ人間として設定はしました。
――そうだったんですか。その『在日ヲロシヤ人の悲劇』の前に、先ほどから話に出ている『ロンリー・ハーツ・キラー』が刊行されていますね。
星野 これははじめての書き下ろしで、雑誌とは違って、締切を設けず出来上ったら提出する、という形で取り組んだ作品なんです。1年間本当に、あの小説だけに専念しました。当時としては自分の中でいちばん長い作品だし、新たな試みへ挑戦というつもりで、自分からあえて「政治小説」と銘打ちました。次のステップに進むための集大成とも言えるし、それまでの5年くらいの代表作みたいなつもりで書いたものです。
最初のモチーフは新聞記者時代に感じたことがスタートになっています。昭和天皇の崩御を取材した時、世の中が自粛モードに染まったことも奇妙に感じましたが、普段は天皇のことを気に留めている人なんてほとんどいなかったのに、死んだとたんにすごく欠落感や喪失感を抱く人が続出したことにも驚きました。
年配の、特に戦前に教育を受けたような人たちならある程度理解できるんですけれど、自分と同世代の若者でも虚脱したりしているのを見て、日本社会で生きてる人って、じつは無意識の根幹を天皇制や天皇という存在に支えられているのかなと思ったんです。だからもし突然、明日から天皇制を廃止しますとなったら、アイデンティティ・クライシスに陥る人が結構いるんじゃないかと考えました。
それで、この小説の第1部は、一種の社会変革の象徴であった若オカミ(皇太子)が消えて、自我を喪失しかける人たちがいっぱい出てくるというところからスタートしているわけです。
――若オカミの死後、引きこもりの若者が増えて、そこで井上という青年が現れてカリスマ的な存在となり、若者たちは血盟団の「一人一殺」じゃないけれど、一人殺して自分も死ぬという行動に走ろうとする。
星野 結局、天皇という自我を喪失して、自死にいくんですよね。自死したとたんに彼らはカリスマになるので、殉死みたいなものです。乃木希典じゃないですけれど、殉死をすれば、若死にすることで社会を変革しようとした若オカミの意志を体現できるんだということになり、それがものすごい勢いでいろんな形で拡大していく。それが第2部になるわけですけれども。
アイデンティティ・クライシスに陥らないで取り残されていく側には、女性や移民が多い。第1部が殉死に傾いていく男の視点で語られるのに対し、第2部と第3部はその女性・移民たちの視点で語られます。殉死に倣う者が続き、さらには若オカミの変革の意志を継いで誰かを道連れにして死のうとか、誰かを殺して自分も死ぬみたいな現象が熱狂的に広がっていく。
――この頃から自殺の問題を意識されていたんですね。
星野 そうですね。でも『無間道』で自殺をテーマにしたのとはちょっとまた違う意識だったんですよ。これを書きはじめた2002年の頃は、社会にこんな経済格差が開いていることがまだ僕の目には見えてなくて、まだ一様な中産階級の社会だと思っていたんです。だから、バブル崩壊後に就職が難しくなったりはしていても、それでも職を選ばなければ何となく食べていける社会だとイメージしていたんですね。
なので、死というのがあまりリアルなものじゃなくて、彼らが殉死する時にも、ある意味すごく抽象的、観念的な死を死んでいるというつもりで書いていました。みんな生きている感触がほしいからこそ、死ぬ行為にどんどん惹かれて連鎖していくのだ、と考えていたんです。
この頃はまだ自尊感情の低さとして捉えてはいなかったんですけれども、自己が空虚であるという感覚は出したかったんですよね。自分たちに生の感覚をもたらしてくれるかもしれなかったオカミが死んで、一緒に死ぬことのほうが生の感覚をもたらしてくれるんだと触発されてしまう。残された数人の女性が、雪崩を打って死に向かっていく社会に違和感を抱えて、必死に留まろうとしているわけです。