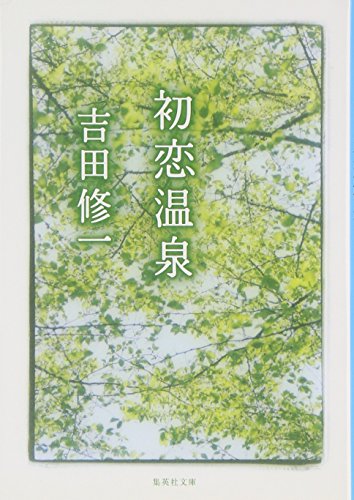犯罪ものを書いてみようと思った理由
――「パーク・ライフ」ではじめてスターバックスが小説に出てきたんじゃないかと言われて、その次に書いたのがバーニーズで……。なんかおしゃれなイメージもありましたよね(笑)。
吉田 ある名物編集者の方にはじめて会った時、「吉田君はもう『パーク・ライフ』のおしゃれ感で一生食べていけるよ」って言われました(笑)。なんの根拠があってそんなことをおっしゃったのか(笑)。でも、普段の僕を知っている朝世さんからすると「おしゃれ? はあ?」って感じでしょう?
――あははは。いやいやいや。で、『日曜日たち』も東京を舞台にした連作短篇で、次の『東京湾景』も東京で……。
吉田 『東京湾景』は読めば分かると思いますが、タイトルはおしゃれっぽいけれど、湾岸の労働者の話ですからね。お台場と、品川ふ頭ですから。バイト時代に実際に品川のあのあたりの倉庫で働いていたことがあるんです。品川のあの感じを書きたいというところからスタートした話です。
――その次が『長崎乱楽坂』ですよ。がらりと変わって。
吉田 ああ、『日曜日たち』、『東京湾景』、『長崎乱楽坂』、『春、バーニーズで』と、短編集の『女たちは二度遊ぶ』(06年刊/のち角川文庫)と『初恋温泉』(06年刊/のち集英社文庫)くらいまでは、全部芥川賞受賞後にほとんど並行して書いていたものです。今、考えると、本当に恐ろしい。
――その間に『JJ』で連載した『ひなた』(06年刊/のち光文社文庫)も書かれていますよ。
吉田 ああ、そうでした。年に4冊とか出していた時期ですね。今はもう変わったんですけれど、当時って出版社でも純文学とエンターテインメントがくっきり分かれていて、同じ出版社でも担当が違ったんです。たとえば文藝春秋だと『文學界』の担当と『オール讀物』の担当が別々の人で、その上、単行本の担当もそれぞれ違ったんです。今は基本的に一社で一人だと思うんですが。
――そうやっていくつもの小説を同時進行で書いたものが一段落し、写真家の佐内正史さんとコラボレートした『うりずん』(07年刊/のち光文社文庫)を経て、いよいよ取り組んだのが『悪人』だったということですか。
吉田 そうですね、芥川賞後に新たに書いたものが一段落して、新聞小説として『悪人』を書くことになって。これも担当者から本当にうまい具合に導かれたなと思っています。97年デビューして、5年目に『パレード』が出て、その5年後の2007年に『悪人』です。『パレード』の時と同じように、「もっと広い世界を見ましょうよ」と暗に言ってくれたんだと思う。きっとそんなことを言われてこっちも調子に乗って、「犯罪ものを書いてみたいんですよ」という話をして。
――なぜ犯罪ものを書きたいと思い、なぜ九州だったのですか。
吉田 考えてみれば、「最後の息子」にしたって、公園でのいわゆる“ホモ狩り”を書いていますし、『パレード』もそうだし、『東京湾景』の犯人のモデルは『悪人』の犯人のモデルでもあるし。昔から何かしらの事件をずっと書いていたので、いつか正面から犯罪ものを書きたいなというのはありました。それでまず浮かんできたのが、冬の三瀬峠のイメージだったんだと思うんですよ。
――人を殺してしまった祐一と逃げることになる光代は、彼女が働いているような国道沿いの量販店を取材旅行で見た時に、ストーリーが変わったというのを憶えています。
吉田 最初は光代も殺される話を考えていたんですけれど、あるショッピングモールで一人の女性が買い物していて、その姿がなんというか、とても楽しそうなのに寂しそうで、その姿を見ているうちにこの人は殺せないと思ったんですよね。小説の中とはいえ、人を一人殺すってことは、本当に大変なんですよ。
――なんで光代という名前にしたんだろう。絶対角田光代さんを思い出してしまう。
吉田 ほんとですよね。原作では双子で、珠代、光代という二人なんですよね。だから書いている時に角田さんのことは浮かんでいなかった。そういえば『平成猿蟹合戦図』(11年刊/のち朝日文庫)を書いた時に、主要人物ではなく、1回しか出てこないような人たちが何人もいるんですが、そのなかに篠田という名前の人が4、5人いたんですよ。指摘を受けて書き換えたんですけれど。それでふっと顔をあげたら、目の前の本棚に篠田節子さんの本があって(笑)。無意識のうちにこれを見ていたんだなって(笑)。