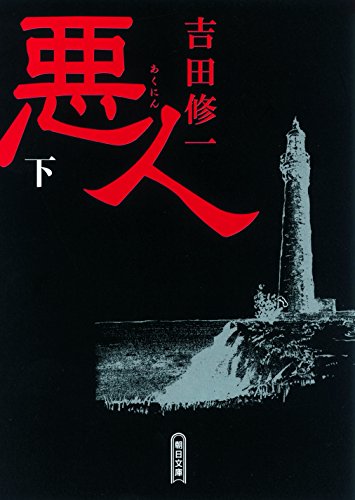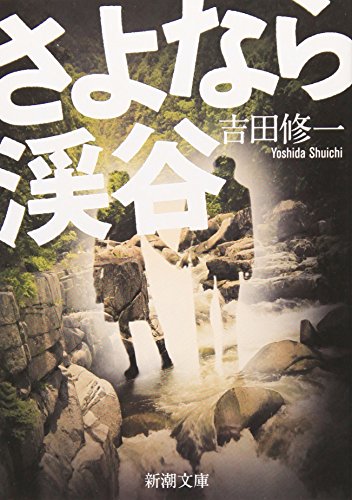いろんな人を巻き込んで、映画も含めて盛り上がった『悪人』
――あはは。すみません、私から脱線させてしまいました。さて、『悪人』は本当に、10年目ですごいものを書いたなという。映画化もされて、大変盛り上がりましたよね。
吉田 そうですね。当時は本当に浮かれていました。映画化もあって、脚本も監督と一緒に書いて、知らなかった世界も見られたし。でも今となってはそこを超えなきゃというのが結構なプレッシャーですよ。
――傑作を書いてしまったばかりに……。
吉田 担当編集者と居酒屋で飲んでいる時に、「タイトルを『悪人』にしようと思うんです」と言った瞬間から、いろんなことが始まったんですよね。最初は本当にたったの二人きりだった。それが、営業部の人たち、応援してくれる書店員さんたち、いろんな人を巻き込んで、その後、今度は映画で盛り上がっていくという初体験の興奮が未だに自分の中に残ってますからね。だからどうしても、そのあとに書いた作品のほうが出来はいいと思っても、なんか超えられないでいるような感じはある。ただ、映画化でいうと、今年は『怒り』(14年刊/のち中公文庫)がありますし、またいい体験ができたらなとは思っていますけれど。
――『悪人』では、私は娘を殺されたお父さん、佳男さんが大学生の男の子に語り掛ける場面で大号泣だったんです。吉田さんはいつも、懸命にあがいている人を書いている。そして、あがく人を見て愚かだなと思って笑っているような人こそが愚かなんだなってことを書いているように思うんです。『怒り』にも、他の作品にも感じることなんですけれど。
吉田 戦っていない人っていないと思うんですよ。それぞれがそれぞれの場所で戦っていると思うんです。たとえば政治家が国を背負って戦うこともあれば、職場で仕事に関しての戦いもある。家族の中での戦いだってあるかもしれない。そうやってそれぞれがそれぞれの場所で戦っているのを、やっぱりちゃんと見なきゃ駄目だとは思っていますね。その中で、今おっしゃった佳男じゃないけれど、それぞれの戦いに大小や優劣なんかなくて、みんながそれぞれの戦いを必死に戦っているんだという思いは強いです。
――そして『悪人』のあとも、とても難しい犯罪について書かれています。『さよなら渓谷』(08年刊/のち新潮文庫)。実際にあった体育会系の集団レイプ事件がベースにありますが、驚いたのは著者インタビューしたときに「これは純愛小説だと思う」と言っていたこと。
吉田 幸せになるために一緒にいるんじゃない、という愛をどう呼べばいいのか分からなかったのかもしれませんね。ただ、分かろうと必死に書いてはいるんですよ。そういえば、今年のアカデミー賞でレディー・ガガのパフォーマンスがあって、その舞台に多くのレイプの被害者たちが勇気を出して出演していました。驚いたのは、その中に少なくない男性が混じっていたことです。今回の『怒り』でもレイプは書いていますが、そういうものに関しては細心の注意を払って自分なりに書いているつもりです。チャレンジではありますけど、何かを書くというのはとにかくチャレンジですからね。