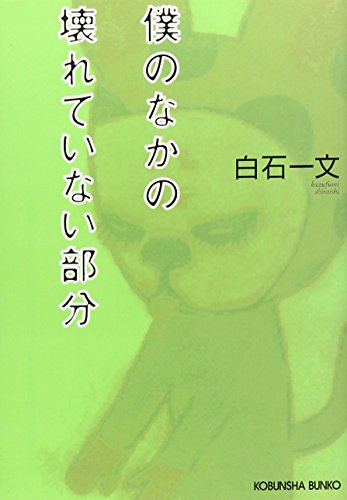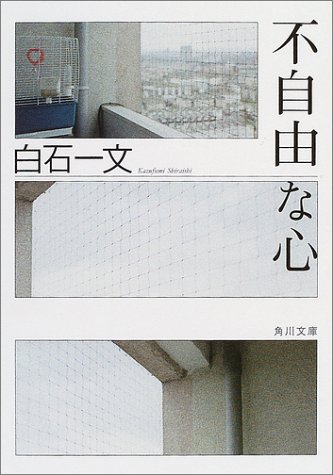初の単行本『一瞬の光』(2000年)が刊行されるまで
――『僕のなかの壊れていない部分』(02年刊/のち光文社文庫)は出版社の社員が主人公ですが、あれは20代の頃に書いたものですか。
白石 学生の時に、原型になるような300枚くらいのものを書いていたので、週刊誌が終わって月刊誌に配属になった時に読み返してみたんですよね。当時はまだ四百字詰め原稿用紙に手書きでした。それで「ああ、これをちゃんと書こう」と思ったんです。書き上げたのは25~6歳の頃かな。その時に主人公を出版社の人間に書きかえました。でもあの主人公の性格や、いろんな女の人と知り合って……というのは、まあかなり妄想が入っていますが(笑)、学生時代の原型にすでにあったものです。
――デビュー前に原型があったものって、他にもあるんですか。
白石 初期のものは全部そうですね。『一瞬の光』とか『不自由な心』(01年刊/のち角川文庫)とか。『すぐそばの彼方』(01年刊/のち角川文庫)という政治の小説は、月刊の「文藝春秋」に移って政治の取材を始めていた頃に書きましたね。選挙制度改革が叫ばれて中選挙区制から小選挙区制へとちょうど移行する時期のことです。あの小説での自慢は、参考文献がないことです。あそこに書いてあることはほとんどが自分自身で取材して手に入れた事実をデフォルメしたものです。あれは『すばる』文学賞の佳作をもらった後に書いたんじゃなかったかな。
――週刊誌時代以外はずっと応募は続けていたんですか。
白石 もう編集者になっているから他社の編集者にも見せましたよ。けんもほろろでした(笑)。社内の人にも見せたかな。自分が書いたと言うとまずいから、「友達がちょっと書いてきたんだけれど、これ読んでくれませんか」とか言って読んで貰うと、「この人、作家になるのはちょっと無理だと思うんだよね」とか言われるわけです。何しろ相手は文春のベテラン文芸編集者だったりするわけですから、すごく的確に、いかに駄目かということを指摘してくれる。こっちは「そりゃ、そうですよね」とか言いながら心の中では泣いているわけです。ものすごく傷ついている(笑)。「やめたほうがいい」と何回言われたか分からないですね。
――すばる文学賞に応募した「惑う朝」という作品が佳作に選ばれるのが1992年、34歳の時です。そこで、もう一篇長いものを書いてデビューしましょうという話になったんでしたっけ。
白石 そうです、結局編集長が代わってその話が流れてしまったんです。もともと認められていなかったんだと思いますよ。もう30歳を過ぎていたので焦りまくっていましたね。佳作にひっかかった時も「なんとか持ち時間を延長できた」という気持ちでした。だって19歳から作家になりたいと思っていて、そこから15年経ってもデビューできなかったらたぶん無理だろうと思うじゃないですか。
――デビューの話が流れてから、どうなったのですか。初の単行本『一瞬の光』が刊行される2000年まで、ずいぶん時間があきますよね。
白石 『すばる』からは長編の話も来ないし、しょうがないから自分でコツコツ書こうと思って。当時はまだ前の女房と一緒で、東京の西のほうに住んでいたんです。「文藝春秋」の編集部にいる頃で、行き帰りの時間がもったいなくて、西新宿にアパートを借りたんです。そこに小さなテーブルを持ち込んでせっせと書いていましたね。校了のあと、眠気覚ましに麹町の会社から歩いて帰って、ちょっとシャワーを浴びて、それから書く。その頃に『すぐそばの彼方』や『不自由な心』という短篇集に入っている短篇なんかを書きました。
でも、まったくあてもなく書いているわけです。で、内心、ちょっと無理かなと思っているんです。それでも二本くらいは『すばる』に載せてもらったのかな。でも、34歳でもう駄目だと思っていたわけですから、40歳が近づいてくると決定的に駄目だと思うわけですね。37~8歳の頃は、会社にいる間に40歳の誕生日を迎えることになったら作家になることは諦めよう、無理だ、と思い詰めていました。だから乾坤一擲、なにか書かなきゃって思ったんです。
――才能を認めてくれたり、応援してくれる人はいたのですか。
白石 小説家になれると言ってくれたのは、うちの父と、藤沢周平さんでした。父は私が若い時に書いた小説を読んでくれて「絶対なれる」と言ってくれたんですよね。
藤沢さんには、私が30代後半の頃、「文藝春秋」で『漆の実のみのる国』という最後の長篇を担当させてもらっているときに「作家になれるよ」って言って貰った。たしか二度目にお目にかかったとき、先生が『すばる』で佳作になった私の作品を取り寄せて読んでくれていたんです。これにはびっくりしましたね。もちろんそんな話、おくびにも出していなかったですから。ご自宅で差し向かいで座っていると、不意に先生が「読んだよ」と言うんです。「先生、冗談はやめてください、私は仕事で来ているんですから」と言ったら、普段はまったく怒らない方なんですけれど「ちゃんと話しているんだから、ちゃんと聞きなさい」ってめずらしく怒られました。藤沢さんご自身も業界紙の記者をやって40歳を過ぎてからオール讀物新人賞を受賞してデビューされている。それで「白石君、40歳を過ぎても大丈夫だから。きみは作家に絶対なれるから」と言ってくれたんですね。
そうそう、石原慎太郎さんには担当になって挨拶に言ったら「きみの『すばる』は俺が佳作にしてやったんだよ」って言われて、その瞬間に「ははーっ」となりましたね(笑)。石原さんは選考委員のお一人で、たしかに私の作品を推して下さったんです。
で、たまたま何かの縁で、講談社の人から「書下ろしをやってみないか」と言われて、それで300~400枚くらいの長編を書いたんです。当時は『涙の化石』というタイトルでした。「なかなかいい」、「ここを書き直してください」などと注文を出されて、これで再デビューできるかなと思って必死になりました。
そうこうしている時に女房と大喧嘩になって家を飛び出したんです。今度は池袋の隣駅にある要町に、収納もなにもないワンルームを借りて、そこで一人で暮らしながら原稿を書き直していたらどんどん長くなって1200枚になってしまって。