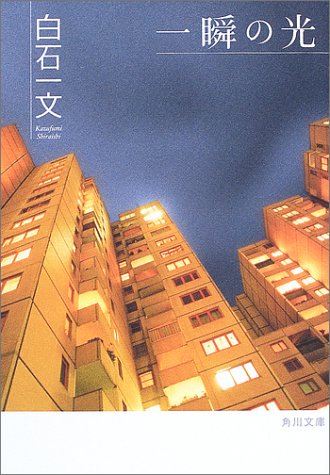よく分からないことが人生にはすごくいっぱいある
白石 で、どんな人との間にもやっぱり、そういうことはあるんじゃないかと。しかもそれが日々、いろんな形で起こっているんじゃないかと……。
私たちは本質的にはすごく孤独で、言葉という非常に精緻なツールを使っても理解しあうことはほとんど不可能なんだけれども、だけど、人が人を求めるという、ある種のダイナミズムは確実に存在している。そして、そのダイナミズムの最も分かりやすいモーメントは性衝動だと思いますが、この小説では性衝動というモーメントがなくても人間同士を連結するダイナミズムそれ自体は常に存在するんだということを書いている。じゃあ、性衝動以外の最も重要なモーメントはなにかというと、不可知な、不思議な出来事なんじゃないかと思っているんですね。
人が「直観」とか呼んでいるものって、実は肝心な時に作用しているそのモーメントなのではないかと思います。出会った瞬間に「私はこの人とつきあうことになると思った」とかよく言うでしょう。他人のそういう話を聞いた場合、そんなの気のせいだとか後付けだとか、「この人とつきあいたいと思っただけでしょ」と私たちは取り合わないのが普通ですが、いざ自分自身のこととなると「運命だ」って真顔で言いますよね(笑)。それが面白いんですけれど。私もそれは運命なのだろうと思います。
そんなふうによく分からないことが人生にはすごくいっぱいある。これまた私の長年の経験において思うのは、不思議なことってなぜかうまく出来ていて、すぐに忘れるようになっているんですよね。憶えていないんですよ、そういうことって。でも、実はね、人が孤独でいないで済んでいるのは、そうした不思議なことの連続のおかげなのではないかと最近思っていますね。誰かと理解しあうとか、理解しあわないということではなく、そっちの方がよほど重要なんだと。
――ベストな相手を見つける、というテーマはずっと書かれてきたものですよね。直木賞を受賞した『ほかならぬ人へ』(09年刊/のち祥伝社文庫)も、『翼』(11年刊/のち鉄筆文庫)も男女の恋愛においての話でしたよね。でも、今作は恋愛とはまったく違う。
白石 変わりましたよね。私自身の性的な欲求が薄くなってきていますからね(笑)。さっき言ったような「運命的なもの」という考えを手放してはいないんですけれど……。ベストな相手のその「ベスト」がどういうことなのか、それが分からないんですよね。男女に限らず、男同士だろうが女同士だろうが、親と子であろうがきょうだいであろうが。やっぱり全然分からない。
――社会的な地位のある男性が年下の女性と知り合い、保護者のように一生懸命世話を焼く。白石さんのデビュー作の『一瞬の光』(00年刊/のち角川文庫)もそこから始まる話でしたよね。
白石 そういえばそうですね。全然気づかなかった。どちらもタイトルに「光」という文字を使っていますね。なんででしょうね。
――気づいていなかったんですか。無意識のうちにそういうモチーフに惹かれるものがあるんでしょうか。
白石 うーん、『翼』などを読んでくれた人には申し訳ない言い方になるけれども、やっぱり私のなかで、恋愛関係が最も優れた、優先順位の高い、価値の大きな関係ではないんじゃないかというのが最初からあるんでしょうね。
――白石さんご自身、実際すごく世話焼きですよね(笑)。
白石 人の世話を焼くのは大好きですよ(笑)。といっても、あくまでもある意味においてですが。自分という人間が人と接触して関わりを持つことが、なんておこがましいことだというのが心の根底にあるんですよね。本来だったら自分みたいな人間が誰かと関わりを持つなんてことはありえないんだ、と。
自分には何の価値もないんだから、他の人が自分みたいな人間と付き合うことには当然価値がない、というのがひとつ。もうひとつは、自分がすごくねじくれている人間なので、その正体がバレたらどうしようっていうのがあるんです。会う回数や話す回数が増えていくと、いくら自分を守っていても、いろんなことがさらけ出されてくるじゃないですか。そうすると好奇心のすごく強い人だったりすれば、私がどういう人間かってことを見抜いてくる。こっちは見抜かれたら大ごとだっていうのがあるわけです。最低な人間だと見破られてしまうんじゃないかという恐れが常にある。できるかぎり人との接触を避けるのは、その防御措置なんですね。
だけど私という人間は、そうは言いながらも人恋しい人なんですよ。だから見抜かれる前にその人の世話をしちゃえっていうのがあるんだと思います。私と会った人は分かると思いますが、やたらに相手の話を聞くじゃないですか。これは世話の第一歩(笑)。
――そうですよ、はじめて著者インタビューでお会いした時、白石さんが私のことをいろいろ質問されるので逆インタビューされている気分でした。あとになって、何人もの人から「自分も白石さんと初対面の時そうだった」と聞きました(笑)。
白石 それもね、人の話を聞いている間は自分の話を聞かれないで済むというのがすごくあるんですよね。自分のなかに自分のことを話すより相手の話を聞いたほうがずっと人間関係として価値があるんだ、という信念みたいなものがある。若い頃にそれをやっていると、女の人に「この人は私にすごく興味があるんだ」と思ってもらえて、仲良くなれたりもしました(笑)。
なんでしょうね、生まれた瞬間からとは言わないですけれど、物心ついた時から、あまり人間のことが好きじゃなかったと思うんです。やっぱり人と会ったり話したりするのがすごく苦手でしたね。