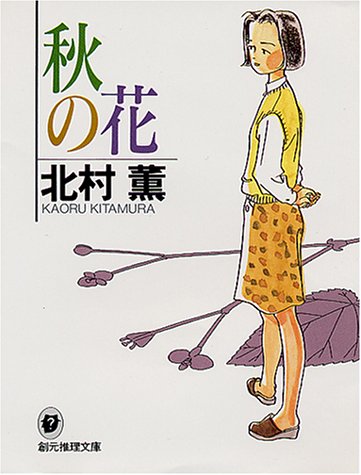「ミステリーを書く時のリアリティ」について
――1989年に「鮎川哲也と十三の謎」のなかの一冊として短篇集『空飛ぶ馬』(のち創元推理文庫)でデビューされます。これも戸川さんに薦められて書いたわけですよね。これがのちに人気シリーズとなる、円紫さんと〈私〉の話だった。
北村 最初の「織部の霊」という短篇を書いたら戸川さんが「なかなかいいよ、すごいよ」と言ってくれて、それで、そのあとも書けたという。
――「織部の霊」のあの話を書くために、女子大生の〈私〉と落語家の円紫さんという組み合わせが生まれたということですか。
北村 そうですね。落語が好きで聞いていると、自分はできないけれど「ここはこういうふうにやったらいいのにな」とか、「この演出はちょっとへんだよな」とか、思うことが出てくるんです。木々高太郎が、『世界的な大哲学者になるのはできないけれど、世界的な大哲学者だということをそれらしく書くことはできる』と言っています。私も落語家にはなれないけれど、落語家を登場させればこんな話、あんな話も書けるし、自分がこういうふうにやったらいいなと思っていることが書けるだろう、と。探偵役は闇を照らす光なので、人間的な物語を担うワトソン役として、〈私〉を登場させました。
そこからはじまって5編を書いて一冊の本になりました。一生に一冊くらい本ができたらという気持ちで書いて、まさかそこからいまだに書いている、しかも好きなことを好きなように書いて続けられているのはありがたいことですね。
――前に何度もおうかがいしていますが、その時は〈日常の謎〉という言葉もなく、ジャンルとして認識されているわけでもなかったと思うのですが。どういうミステリーを書こうと思われていたのでしょうか。
北村 それは書く時のリアリティですよね。やはり毎度言いますが、探偵が何度も何度も殺人事件に遭遇しているとすれば、もうその探偵が犯人としか思えないっていう(笑)。ということはやはり変だなと思うので書けないので。でも、どちらがアンチリアルかと考えると、そういう殺人のほうが、実は起きているかもしれないですけれどもね。
――砂糖合戦よりも。
北村 そう。しかし書くうえのリアリティということを考えていくと、私にとっては砂糖合戦のほうがリアルだったという。
――以前、殺人を書くとなると、加害者の家族や、遺族のことなども考えてしまって難しい、ということもおっしゃっていましたよね。
北村 無理にやればね。だからもし書くとなると、そこまで考えてしまう。たとえば『秋の花』(91年刊/のち創元推理文庫)は、亡くなった子のお母さんがいちばん最後に出てきますよね。そこまで書かないと、ということです。
――そう、〈日常の謎〉というと「人の死なないミステリー」と言われることもありますが、〈私〉シリーズの『秋の花』では女の子が亡くなっています。私は学生の頃に読んだのですが、私の本を借りて読んだ父が「許すことはできなくても、救うことはできる」という、あの部分を絶賛してまして。自分もあとから振り返って、北村さんはやっぱりこの頃から、生きづらいなかでも生きていく姿を書いていたんだなと思って。謎解きの面白さもあるけれど、人間の根底の部分を揺さぶるようなものを書かれますよね。
北村 そうですね。なんか身構えて書こうということではなくて、表現をしていれば自然とそうなりますね。そこまで深刻に心揺さぶるものでなくても、ちょっとした心のあやもありますしね。人間は心を持つ生きものなので。書いているとそういうものが出てくる。
――時と人の三部作の『スキップ』(95年刊/のち新潮文庫)、『ターン』(97年/のち新潮文庫)、『リセット』(01年刊/のち新潮文庫)も、それぞれいきなり25年後の世界にいたり、同じ日を繰り返したり、再びめぐりあったりと、時間の流れというものが大きなテーマになっている。そのなかで、生きていく困難さとどう向かい合うのかということが描かれていると思うんです。
北村 すごく小さな頃、いつかは死ぬということが、すごく大きな恐怖としてあったので。有限性の残酷さというのかな。それはどんなにジタバタしても逃れられない、怖いことですよね。だから『秋の花』でも、〈私〉は自分より前に生まれた人間が亡くなることは理解できる。でも、自分よりも後に生まれた人の死は、時間は有限であることをまざまざと見せつけられるものだったんですよね。