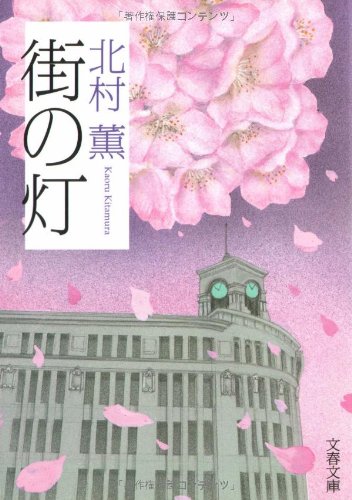書かれざるところでそのまま生きていた、登場人物たち
――確かに。身の回りで遭遇した謎にぴったりの登場人物は誰かと考えるとそうなりますね。それで、昨年『太宰治の辞書』(15年新潮社刊)が出来上がったわけですね。デビュー作でもある落語家の円紫さんと主人公の〈私〉の日常の謎シリーズ、実に17年ぶりの新作。
北村 きっかけは、一昨年の秋に別の用事で新潮社に行った時に、新潮文庫創刊100年記念で作られた創刊当時の完全復刻版を見せてもらったことですね。このあたりは小説に書いた通りです。巻末の刊行案内にピエール・ロチの名前があるのを見て、ああ、芥川龍之介の「舞踏会」の題材となった「江戸の舞踏会」を書いた人物だなと思ったんです。ちょうど『小説新潮』に短篇を書くことになって、ピエール・ロチのことや三島由紀夫が雑誌の座談会でロチの名前を間違ったことに思いを巡らせているうちに、太宰治の辞書についてまで考えが広がって、これで小説が書けると思った。ここまで細かく考える主人公は誰だろうかとなった時に、〈私〉しかいないんじゃないか、と思ったわけです。
――それで、東京創元社からではなく新潮社からの刊行となったわけですね。この作品でも北村さんの〈読み〉の達人っぷりを堪能しました。太宰の『女生徒』で、電車の中で他の人に席をとられる場面の不自然さを指摘している。自分は以前読んだ時にそこは気付かず、言われてみればああそうか、と驚きました。
北村 だってあまりに不自然じゃない。目の前に立っていて荷物が置いてあるのに、脇から来た人が荷物をどけて座ってしまうなんて。ありえないことは、おかしいなと思うのが自然でしょう。引っかかるんですよね、棘として。それで、あっそうかこういうことかと分かった時に、やっぱり快感があるんです。こういう仕事をしていなければ、あっそうか、で3歩歩いたら忘れちゃうようなことだけど、それを書きとめておこうとすると本になるという。
――登場人物たちがちゃんと17年分、年を重ねていて胸がいっぱいになりました。
北村 書かれざるところでそのまま生きていた、ということですよね。なんでもそうなんです。たとえば『街の灯』(03年刊/のち文春文庫)のベッキーさんシリーズでも、私はあそこで終えて最善だったと思っていますが、戦後にみんなどうなっているのかはあるわけです。
――昭和初期、お嬢様の英子とその博学な女性運転手、ベッキーさんを主人公にしたシリーズですね。三部作の最終作『鷺と雪』(09年刊/のち文春文庫)で直木賞を受賞されています。物語は二・二六事件の年に終わりますが、彼女たちのその後についても、作者の頭の中にはあるわけですか。
北村 書く必要はないので書きませんけれど。あれは二・二六の電話がかかってきて、非日常の中に日常が食い入る。その怖さに行きつくために書いた話なので。別宮は何もできないのです、できるのはこれを読んでいるあなたたちです、という意味をこめたかったので。