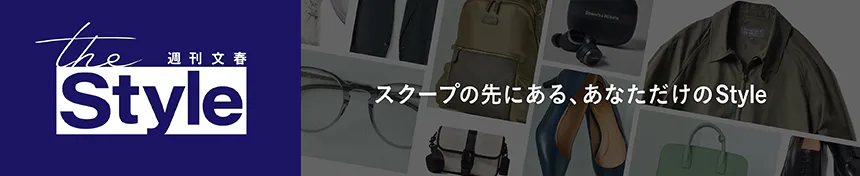誰もいない市街の映像はインパクトがあって視聴者に刺さるし、2年間で撮り貯めたかつての時期のものと並べて、「今回は人出の減り方が鈍く、気の緩みが……」といったストーリーも作りやすい。コンテンツとして美味しいわけです。
浜崎 理性ではなく、末梢神経の刺激に訴えるわけですね。
調和を乱すものは“悪”
與那覇 しかも私たちの五感のうち、視覚だけが極端に過敏になっている。だからグラフに図示される「増えた、減った」ばかりに感情を操られ、「致死率が低い変異株の、感染自体を忌避する必要があるのか?」と問い返すことができない。
浜崎 これまで日本人は、目の前の枠組みに適応することばかりを考えて、その枠組み自体を問うという意識が薄かった。だからその歪みが、危機のたびに現れてくるんでしょう。
私は、コロナ騒動を機に、色々と日本人論を読み直しているのですが、たとえば福田恆存は、日本人は「浄か、不浄か」、「きれいか、汚いのか」の価値判断で動くと言いますが、この「きれい」の定義は、共同体内の「調和」なんですね。
何が正しいのかは二の次で、とにかく調和を乱すことは許さない。本音を言って事を荒立てることはしないわけです。しかし、本当の問題は、そんな「事なかれ主義」の性格を日本人自身が自覚してこなかったことで、だから、自分の無意識に振り回されることになるんでしょう。
與那覇 戦後日本の知識人の多くが批判してきた、私たちの思考の悪癖ですね。山本七平は「空気に水を差す人」が排除される現象を、丸山眞男は「純粋な『きよき心』が無謬視される」問題を指摘しました。
浜崎 あるアンケートでマスクをする理由を尋ねたら、「感染防止のため」という回答はごくわずかで、「皆がしているから」という理由が圧倒的に多かったそうです。だからマスクを外している人間に対しては、「皆がマスクしているのに、けしからん」となる。
與那覇 「和を以て貴しとなす」は、裏返ると同調圧力に転じます。
浜崎 日本人の同調圧力の問題は根が深いですね。近代以降、故郷や共同体など、自分が拠って立つ場所を失った日本人は、どう他者と関わったらいいのかが見えなくなってしまった。その不安が、同調圧力で危機を乗り越えようとする日本人の悪癖を加速させてしまった。実際、不安ベースのコミュニケーションは、自己喪失者の典型的症状です。