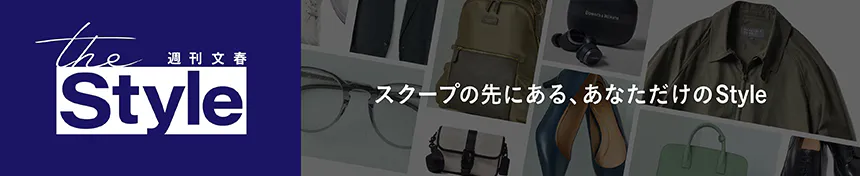大正から昭和初期にかけて北海道の山野を跋渉して狩猟、渓流釣り、登山、植物採集、鉱石発掘などに明け暮れた開拓者・西村武重。
これまで100頭以上の熊を目撃した彼だが、中には体重450キロを超えるものもいた。牛馬を食い殺し、人間の腹をえぐる“超弩級の大熊”を相手にどう戦ったのか? 著書『北海の狩猟者』の一部を抜粋。(全2回の1回目/後編を読む)
◆◆◆
このところ、北海道はうちつづく冷害、凶作に苦しんでいる。農民たちは文字通り、今日明日の生活に喘ぎつづけているのだ。
だが、これは人間ばかりではない。けものたちもまた同じで、野山のブドウ、コクワなどのみのりがなく、餌を漁って山をおり、収獲の少ない田畠を荒らし、人畜に危害を加えはじめた。
特に、日本の百獣の王ともいえる羆の出没横行は、山村の人たちを震えあがらせており、各地で被害が叫ばれている。
家の近くに繫いである綿羊はさらっていくし、昨日までいた放牧中の牛や馬が突如見えなくなったと探しまわると、やっと発見されるのは喰い荒らされた残骸という例も多い。ひどいのになると、軒先に繫いである乳牛を殺して喰うという、おそるべき暴君ぶりなのである。
目の前には巨大な羆、殺されると思ったが…
――北海道でも、特に鮭で有名な根室の、西別川のほとりに虹別という小さな集落がある。阿寒国立公園の摩周湖に隣接するこの地帯は、酪農郷であり、乳牛をもたない農家はほとんどなかった。桑野さんという農家もその一軒である。
おりから晩秋の収穫期。凶作のため例年の二分か三分といった出来だが、それでも生命(いのち)の綱の食料である。取りいれに汗を流し、疲れたからだをウツラウツラと横たえたある晩のことであった。
庭先きのチャツ(牧柵)のなかへ、山からおろしてきていれてある牛の時ならぬ気配に家人はハッとして目を醒ました。なにかひどく恐怖している鼻息がきこえ、どしん、どしんという地響きがするのだ。
主人は懐中電灯を照らしながら、牛の悲鳴のきこえるチャツへ行くと、淡い懐中電灯の光のなかにうす黒いものがうごめいている。
「はてッ、ベコのやつ、なんしているのだろう……」
そう思いながら、丹前姿で下駄をつっかけたままズカズカと近づいた。
その途端、ウオーッと目の前に巨大な羆が立ちあがったのだ。ハッとしたが、もう遅い。大きな前足でグッと抱えこまれてしまった――。あとはもう無我夢中、殺される……という気持がかすかに脳裡をかすめさったまま憶えがなかったという。
十数分がたった頃、家族の者は、外へ出たきりなんの音もしない父親の挙動に不審をもち、変だぞ――というわけでランプをさげてドヤドヤと戸外へ出た。その人声とランプの光とにおどろいてか、羆は逃げていってしまったらしい。