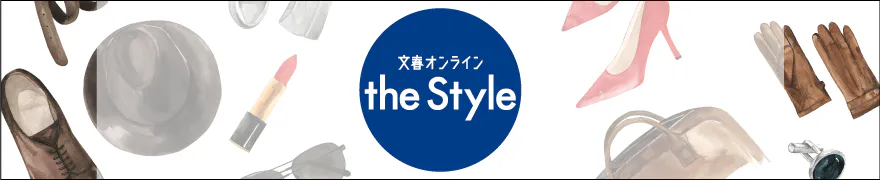舞妓が受けていた“理不尽な仕打ち”とは
告発後の花街の動きについて、桐貴さんはこう語る。
「花街と共存関係にある方からすると、告発を支持できない事情があることもよくわかります。でもこうやって隠すから、何も変わらないんです。いままで苦境を口にする舞妓さんがいなかったことや、私やほかの関係者が声を上げてもそれを否定する声がこれだけ出てくるのは、やはり花街ならではだなと感じます。
舞妓は『5年奉公』『6年奉公』など、修業を始める前に6~10年の奉公期間を約束します。その期間はお母さん(置屋の主人)から言われるように舞などの訓練をしたり、お座敷に出たり。約束の期間を満了する前に辞めることは裏切り行為で、場合によっては数千万円の違約金を求められます。置屋は芸を磨くための“研修の場”であり、舞妓は“修業中の身”。お母さんへはもちろん、なにがあっても芸舞妓の口答えは絶対に許されないんです」
“修業中の身”である舞妓はいかなる理不尽にでも耐えなければいけない。そういった認識は周囲にも、そして舞妓自身にも深く根を張っているという。
「日常的に暴言を吐かれたり、整形させられたり、お母さんの飼い犬の残したささみを食べさせられたり……。ひどい仕打ちを受けた舞妓さんを私はたくさん知っていますが、『修業なのだから厳しくて当然』とか『忍耐が足りない』と片付けられてしまう。私がセクハラや未成年飲酒について花街で相談をしても、『悪口』や『愚痴』程度にしか受け取られませんでした。
花街において、舞妓さんは“何もわからない子ども”。純真無垢で、ひたむきでなければいけません。周囲からそう求められることで、舞妓さん自身もそういう認識を内面化してしまうんです」
「舞妓の上にお客様がまたがって腰を上下させたり...」
しかしながら舞妓の多くは10代後半。“何もわからない子ども”では決してない。桐貴さんは「まだ話していないこともあります」と、現役時代の“理不尽”についてその詳細を語り始めた。
「実際、私もお客様からのセクハラは、意味が分かっていただけに心底苦痛でした。着物の身八ツ口や裾に手を入れられることはもちろん、横になった舞妓の上にお客様がまたがって腰を上下させたり、反対にお客様の上に舞妓がまたがることもありました。また、舞妓のお座敷芸に『しゃちほこ』という三点倒立をする芸があるのですが、その際に着物の裾を広げて下着を覗き見られることも……。
でも舞妓さんは“子ども”なので『性的な知識がないから恥ずかしがらない』という建前があります。だから『わからしまへん』と返すしかないんです」