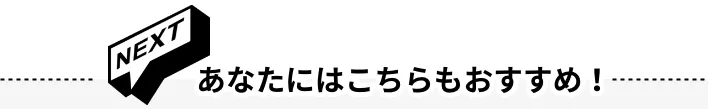1ページ目から読む
8/8ページ目
母が、かつての虐待を完全に忘れていたのか、しらを切っているのか、どちらかは今もわからない。私にとっては、どちらでもいいのだ。
ただ一つ、言えること。あのとき、私が望んでいたこと。それは、母に認めてほしかったのだ、過去の過ちを――。そして、抱きしめてほしかったのだ。それが、母が私に正面から向き合うということにほかならないからだ。
私にとっては消し去りたい暗部で、目を背けたい出来事だが、自分を戒める懺悔の思いと共に、当時のことをありのままに記しておきたいと思う。
私は、おぞましいほどの家庭内暴力を、母に対して幾度となく繰り返した――。私たちはまさに死の瀬戸際にあった。お互いの生死を懸け、悲しみに満ちた苦闘は果てしなく、終わることがなかったのだ。
私にとって引きこもりは、耐えがたいストレスの連続だった。母は、私の家庭内暴力がいつ起きるか、ビクビクするようになっていた。私は、そんな母の態度にもイライラした。
“人生が詰んだ”私は、これからどうなってしまうのか。確かなのは、その先には闇しか広がっていないということだ。母が敷いたレールから外れてしまった私に、明るい未来なんてあるわけがないのだ。私は、日々押し寄せる不安でいっぱいだった。そして、その元凶をつくり出したのは、母なのだという怒りと悲しみに支配されていた。
私と母は、殺し殺されるほんの一歩手前にいたと思う。
菅野 久美子(かんの・くみこ)
ノンフィクション作家
1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)、『家族遺棄社会 孤立、無縁、放置の果てに。』(角川新書)などがある。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆している。
ノンフィクション作家
1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)、『家族遺棄社会 孤立、無縁、放置の果てに。』(角川新書)などがある。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆している。