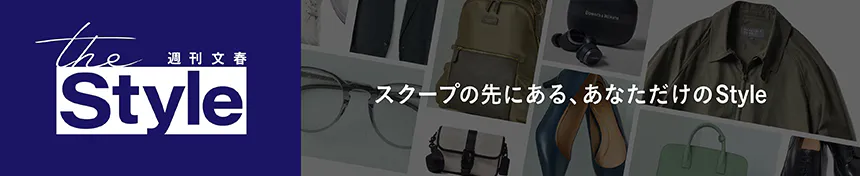道尾秀介さんが、大人気の「リアル脱出ゲーム」を企画運営するSCRAPと組んで制作した犯罪捜査ゲーム「DETECTIVE X CASE FILE」シリーズが大きな話題を呼んでいます。一方、小説と写真を融合させた「いけない」シリーズも累計55万部と多くの読者を獲得、道尾さんが仕掛ける“体験型”ミステリーの広がりはとどまるところを知りません。
小説とは一味違うエンターテインメントが生まれた経緯、そして“体験型”ミステリーの可能性とは? 道尾秀介さんとSCRAP代表・加藤隆生さんが語り尽くします。(「オール讀物」2023年7月号からの転載です)
脱出ゲームとフェアネス
道尾 僕が行くようになったのはここ10年くらいですけど、加藤さんがリアル脱出ゲームの企画運営を始めたのは2007年でしたっけ。
加藤 はい。その頃、僕は京都でバンドをやっていて、宣伝のためにフリーペーパーを作っていた。その企画の一環として考えたイベントがリアル脱出ゲームの最初です。
簡単に言うと、色んな場所に閉じ込められた人が、制限時間内に謎や暗号を解き明かして脱出にチャレンジするというものです。場所はマンションの一室だったり、夜の遊園地だったり、広大なスタジアムだったり。人数も、2人で閉じ込められることもあれば1万人のこともあって、ゲーム形態は様々ですが。
道尾 僕はもともとホラーというジャンルも好きなので、まず行ったのは別の会社が運営する「オバケン」というミッションクリア型のお化け屋敷だったんです。そこで生まれて初めて、自分が映画や物語に入り込んだような強烈な感覚を味わった。たちまち脱出ゲームの虜になり、元祖であるSCRAPのリアル脱出ゲームに行ってみると、謎のクオリティがとにかく高い。「こんなの分かるか!」と苛立つようなアンフェアさが一切ない。やっぱり元祖は凄いな、と通い詰めるようになりました。
加藤 僕自身、アンフェアが気になるタイプというか、楽しみつつも粗探しする嫌なミステリーファンだからですかね(笑)。子供の頃、ミステリーが好きで、小学5年生にもなると「少年探偵団に入りたいのに、もう少年ではなくなってしまう」と焦ったり。その後、ファミコンの「ポートピア連続殺人事件」など、ゲームの世界でミステリー作品が続々と作られるようになったんですが、矛盾や作りの粗さが気になって、子供心にずっと怒っていました。その反動で「ミステリーゲームとは、謎解きとは、こうあってほしい」という理想をコツコツ溜めて生きてきたので、フェアネス意識は制作側になる前から高かったのかもしれないです。